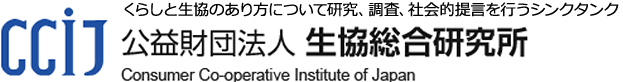- ホーム
- 刊行物情報
- 生活協同組合研究バックナンバー一覧
- 2002年度
生活協同組合研究バックナンバー一覧
2002年度
2003年3月号(Vol.326)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 国立大学の法人化と大学生協 | 兵藤 釗 |
| ■特集 生協のガバナンス改革の到達点 | |
| 協同組合におけるコーポレート・ガバナンスの基本問題 | 関 英昭 |
| コーポレート・ガバナンス改革と経営者責任 | 麻生 幸 |
| 生協の機関運営改善の到達点 | 清藤 正 |
| 21 世紀型生協をめざした首都圏コープグループの運営改革 | 唐笠一雄 |
| 生協における監査の実情と生協監査基準 | 齊藤 敦 |
| ■研究と調査 | |
| 21 世紀前半のスウェーデンの環境戦略─「福祉国家」から「持続可能な社会」へ─ | 小澤徳太郎 |
| 家庭におけるエネルギー消費についての調査 ─電力消費を1年モニタリングした2 件の事例─ |
近本 聡子 |
| ■シリーズ・現代日本生協運動史によせて No.4 | |
| 『現代日本生協運動史』を読む─生協事業の観点から─ | 田代 洋一 |
| ■協同の実践 | |
| 自助と共助をかかげて─災害救援ネットワーク北海道の取り組み─ | 西村 一郎 |
| ■自然科学コラム No.48 | |
| イネゲノムの解読 | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.12 | |
| G.フータルトとS.カーロイ | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.24 | |
| 暮らしの改革指数 | 川名 英子 |
| ■文献紹介 | |
| 佐藤慶幸著『NPO と市民社会──アソシエーション論の可能性』 | 栗本 昭 |
| 井上邦彦著『トヨタ生協革命──苦境からの脱出──』 | 潮見 亜斗矛 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2003年2月号(Vol.325)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 自然の再生に思う | 廣井 敏男 |
| ■特集 食品流通の課題─サプライチェーン・マネジメントの構築の視点から─ | |
| 食品流通におけるサプライチェーン・マネジメントの意義と展望 | 木立 真直 |
| フード・サプライチェーン・マネジメントへの胎動 ─英国のミルク・サプライチェーンを事例として─ |
矢坂 雅充 |
| サプライチェーン・マネジメントシステムの展開 | 鎌田 利弘 |
| 生協青果物事業の基本はSCM ではなく産直(生産者・消費者の協働事業)で ─SCM 視点だけでは本質的には何も解決しない─ |
中島 紀一 |
| ■研究と調査 | |
| 新しい時代の消費者政策の在り方について(下) | 落合 誠一 |
| 「生協係」の仕事と意識─日本生協連学協部会委託調査報告─ | 河原 英夫 |
| ■シリーズ・現代日本生協運動史によせて No.3 | |
| 70年代の共同購入の自立した事業への発展とその教訓について | 田辺 凖也 |
| ■協同の実践 | |
| アジアの友と生きる─(社)アジア協会アジア友の会のチャレンジ─ | 西村 一郎 |
| ■自然科学コラム No.47 | |
| 地産地消 or 地産全消 !? | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.11 | |
| E.アンセーレとL.ベルトラン | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.23 | |
| デフレの現状 | 川名 英子 |
| ■文献紹介 | |
| 朝倉美江著『生活福祉と生活協同組合福祉:福祉NPOの可能性』 | 山口 浩平 |
| ロバート・B ・ライシュ著,清家 篤訳『勝者の代償──ニューエコノミーの深淵と未来』 | 河原 英夫 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2003年1月号(Vol.324)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 子どもたちと食の教育 | 蓮見 音彦 |
| ■特集 子どもの食生活と生協の役割──20 年間の全国調査から | |
| 意識・知識・行動のバランス~食教育 | 八倉巻 和子 |
| 子どもの目で食卓をみる | 室田 洋子 |
| 子どもの食生活調査から生協に求められていること | 西村 一郎 |
| 子どもの食と生協運動──コープながの・健康応援団の取り組み── | 清水久美子 |
| 商品開発に子どもの意見を反映させて──ちばコープ・プチ肉まん開発物語── | 水口和典 |
| パネルディスカッション;子どもの食生活と生協の役割 | |
| ■研究と調査 | |
| 新しい時代の消費者政策の在り方について(上) | 落合 誠一 |
| ■自然科学コラム No.46 | |
| 食と農のキーワード | 川口 啓明 |
| ■協同思想の源流を探る No.10 | 菊地 昌子 |
| シャルル・ジード | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.22 | |
| 産業の空洞化 | 川名 英子 |
| ■文献紹介 | |
| 横溝雅夫+北浦正行著『定年制廃止計画──エイジフリー雇用のすすめ──』 | 川名 英子 |
| 坂本龍一+河邑厚徳編著『エンデの警鐘』 | 鈴木 岳 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年12月号(Vol.323)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 配偶者に関する控除とライフスタイルの選択 | 大沢真理 |
| ■特集 非営利・協同組織をめぐる研究動向 | |
| 非営利組織研究と協同組合研究との関連に関する一考察 | 塚本 一郎 |
| 社会変革を導く社会起業家とは | 服部 篤子 |
| 地域経営とコミュニティ・ビジネス | 金森 康 |
| 社会的企業という概念をめぐって | 山口 浩平 |
| ■研究と調査 | |
| 大津荘一 | |
| 欧州協同組合の倫理政策と行動 | 吉田英子 |
| アメリカにおけるジョブシェアリング | デボラ・シュタインホフ |
| ■シリーズ・現代日本生協運動史によせてNo.2 | |
| 思い出すことなど─「現代日本生協運動史」読後感─ | 嶋根善太郎 |
| ■協同の実践 | |
| 賀川豊彦と21 世紀を生きる | 西村 一郎 |
| ■自然科学コラム No.45 | |
| 健康情報のウソ・ホント | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.9 | |
| J.M.ラドロウとウェッブ夫妻 | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.21 | |
| 人々の生活に明るさ | 川名 英子 |
| ■文献紹介 | |
| 『雑感集 コープみやざきが考えてきたこと・深めたいこと』 | 西村 一郎 |
| 谷本寛治・田尾雅夫編著『NPO と事業』 | 山口 浩平 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年11月号(Vol.322)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 内側へ向かう協同から,外へ拡がる協同へ ─協同組合間協同の在り方についての再考─ |
田中 学 |
| ■特集 災害支援と生協の役割 | |
| 災害に強い社会と市民力─阪神・淡路大震災の教訓 | 室崎 益輝 |
| 阪神・淡路大震災後の災害救援の取り組みと生協の役割 | 山添 令子 |
| 三宅島噴火災害支援と東京の生協 ─避難生活から帰島,そして復興に向けて─ |
生原 勇 |
| 東海沖地震と防災訓練で実感できたこと | 渡辺 英三 |
| 自然災害時における市民活動と生協 | 村井 雅清 |
| ■研究と調査 | |
| 食品表示に関する組合員意識調査 | 日本生協連政策企画部 |
| ■シリーズ・現代日本生協運動史によせてNo.1 | |
| 戦後初期生活協同組合の特徴─とくに町内会・産報転身型生協について─ | 相馬 健次 |
| ■協同の実践 | |
| 賀川豊彦を訪ねて | 西村 一郎 |
| ■自然科学コラム No.44 | |
| 策定された新・生物多様性国家戦略 | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.8 | |
| V- A.フーバーとF.ラサール | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.20 | |
| 男女共同参画白書 | 川名 英子 |
| ■文献紹介 | |
| 相馬健次著『戦後日本生活協同組合論史』 | 栗本 昭 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年10月号(Vol.321)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| BSE ,偽装表示問題,食品安全基本法が提起する研究課題 | 藤岡 武義 |
| ■特集 ライフデザイン | |
| 変化するライフデザイン | 松田 茂樹 |
| 雇用の多様化とマルチ・ライフ─新時代の「働き方」 | 北浦 正行 |
| 住宅資産─特に住宅─を活用した老後生活の安定策 | 喜多村 悦史 |
| 家族とコミュニティのライフデザイン | 宮垣 元 |
| 共済をきっかけにくらしのあり方を追求 ─生協のライフプランニング活動─ |
前田 かおり |
| 組合員のくらし設計をお手伝い ─4 生協のライフプランアドバイザー活動─ |
菊池範子 玉田左美子 山田まさみ 高浦美穂 |
| 食の安全とフードシステム | 高橋 正郎 |
| 地域生協と共済事業の課題 | 矢野 和博 |
| カルタヘナ議定書と遺伝子組み換え作物 | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| G.マッツィーニとF.ヴィガーノ | 鈴木 岳 |
| 公共料金 | 川名 英子 |
| 千田明美著『ほほえみに支えられて:コープこうべくらしの助け合い活動19 年間の歩み』 | 西村 一郎 |
| 中川雄一郎著『キリスト教社会主義と協同組合:E.V.ニールの協同居住福祉論』 | 都築 忠七 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年9月号(Vol.320)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 96 歳のボランティア | 宮坂富之助 |
| ■特集 ワークシェアリング | |
| ワークシェアリングとは何か | 脇坂 明 |
| 雇用の分配か,分断か─日本的ワークシェアリングの落とし穴─ | 竹信三恵子 |
| ワークシェアリングのオランダ・ウエイ | 根本 孝 |
| ■特集 アウトソーシング | |
| アウトソーシング活用による顧客価値の創造 | 笠原 英一 |
| 首都圏コープのグループ企業とアウトソーシング | 濱口 廣孝 |
| 物流業務における子会社とアウトソーシング | 笠原 貞雄 |
| ■研究と調査 | |
| コーペラティブ・グループにおける機会均等政策 | 山内 明子 |
| ■シリーズ・生協経営を考える⑥ | |
| 組合員活動と社会的貢献 | 矢野 和博 |
| ■自然科学コラム No.42 | |
| このコシヒカリは本物? | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.6 | |
| ルイ・ブランとレオン・ワルラス | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.18 | |
| 消費者マインド | 川名 英子 |
| ■文献紹介 | |
| 京極高宣著『生協福祉の挑戦』 | 山口 浩平 |
| 神野直彦著『人間回復の経済学』 | 石塚 秀雄 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年8月号(Vol.319)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| ディーセント・ワーク | 中川雄一郎 |
| ■特集 若い世代と生協 | |
| 生活協同組合と若年世代─ガバナンスと事業,運動の観点から─ | 杉本 貴志 |
| 若者に目を向けた事業と活動─みやぎ生協台原店の事例から─ | 川島美奈子 |
| 単身者(20 ~30 代)の食生活 | 中塚 千恵 |
| 手早く食べられるものが手早く買える ─24 時間営業に踏み切ったイオン「マックスバリュ」─ |
河原 英夫 |
| ■研究と調査 | |
| 衣料用洗剤はどう使われているか | 河原 英夫 |
| ■シリーズ・生協経営を考える⑤ | |
| 生協における人事労務と経営組織について | 矢野 和博 |
| ■協同の実践 | |
| 菜の花に未来を託して─滋賀環境生協のチャレンジ─ | 西村 一郎 |
| ■自然科学コラム No.41 | |
| 保健機能食品と栄養機能食品 | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.5 | |
| チェルヌィシェフスキーとバーリン | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.17 | |
| 京都議定書 | 川名 英子 |
| ■文献紹介 | |
| 青柳斉著『中国農村合作社の改革─供銷社の展開過程─』 | 栗本 昭 |
| 生協総合研究所理事会報告 | |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年7月号(Vol.318)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 大きくて弱い政府から小さくて強い政府へ | 野尻 武敏 |
| ■特集 個配事業の到達点 | |
| 生協における個配の現状と課題 | 堀田 修 |
| 首都圏コープグループの,個人宅配からパルシステムへの変遷 | 若森 資朗 |
| 「個」を基本とした組織改革の取り組み ─個から協同へ~エルビジョン21 がめざすもの─ |
本郷 靖子 |
| さいたまコープの個配の到達点 | 斉藤 真澄 |
| 「ネットスーパー」の現状と課題 | 大澤 理 |
| ■研究と調査 | |
| アメリカの消費者と買物動向 | デボラ・シュタインホフ (翻訳:河原英夫) |
| ■シリーズ・生協経営を考える④ | |
| 地域生協における管理制度の諸課題 | 矢野 和博 |
| ■協同の実践 | |
| 障害者との出会いの場を広げ─財団法人国際障害者年記念 ナイスハート基金─ | 西村 一郎 |
| ■自然科学コラム No.40 | |
| 食中毒の予防法 | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.4 | |
| G.J.ホリヨーク | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.16 | |
| 景気循環 | 川名 英子 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年6月号(Vol.317)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 変革時代に生活協同組合はリーダーシップをとりうるか | 盛岡通 |
| ■特集 食生活の変化 | |
| 若年組合員の食生活と,対応視点─「若い組合員の食のゆくえをさぐる」から─ | 三沢ひろこ |
| 若い組合員の食のゆくえをさぐる─働く主婦の食品ニーズ調査Ⅱ報告─ | 日本生協連くらしと商品研究室 |
| 義務と張り合いのはざまで─働く主婦の食品ニーズ調査Ⅱ定性調査より─ | 近本聡子 |
| おいしさの価値の変化 | 小西雅子 |
| 中食ビジネスの動向 | 山腰光樹 |
| ■研究と調査 | |
| 見直そう,産直野菜の土づくり ─野菜の硝酸問題,生ごみリサイクルをめぐって─ |
後藤逸男 |
| スペインの社会的経済の特徴 | 石塚秀雄 |
| ■シリーズ・生協経営を考える③ | |
| 店舗の赤字克服にむけて | 矢野和博 |
| ■協同の実践 | |
| 子どもの夢をかなえて─広がるメイク・ア・ウィッシュの輪─ | 西村一郎 |
| ■自然科学コラム No.39 | |
| 輸入農産物は農薬まみれ? | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No..3 | |
| シュルツェ- デーリッチとライファイゼン | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.15 | |
| 進む少子高齢化 | 川名英子 |
| ■文献紹介 | |
| ワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン編 | |
| 『どんな時代にも輝く主体的な働き方──ワーカーズ・コレクティブ法の実現を』 | |
| ピーター・キャペリ著,若山由美訳『雇用の未来』 | |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年5月号(Vol.316)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| スキマのある社会と働き方 | 天野正子 |
| ■特集 食料問題とグローバル化 | |
| 世界の食料-先進国と途上国のそれぞれの課題- | 嘉田良平 |
| 多国籍アグリビジネスによる農業・食料セクター再編の性格と動向 | 磯田宏 |
| WTO農業交渉と食料貿易-食料・農業の特殊性に配慮した交渉が必要 | 服部信司 |
| 実質的食糧法改正の進展と未完の「米」改革 | 吉田俊幸 |
| トレーサビリティーと消費者の信頼-フランス牛肉の事例から- | 中嶋康博 |
| ■研究と調査 | |
| 農畜産物の虚偽表示問題と生協産直の課題 | 中島紀一 |
| ■シリーズ・生協経営を考える② | |
| 共同購入の現状と課題 | 矢野和博 |
| ■協同の実践 | |
| 自分流子育てのすすめ | 西村一郎 |
| ■自然科学コラム No.38 | |
| たばこと肥満とやせ-健康を守るには | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.2 | |
| サン-シモンとシャルル・フーリエ | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.14 | |
| 国民生活白書(平成13年度) | 川名英子 |
| ■研究所を訪ねて No.14 | |
| 有限会社 素敵なくらし研究所 | 西村一郎 |
| ■文献紹介 | |
| 門倉貴史著『日本「地下経済」白書』 | |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年4月号(Vol.315)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| マーケティング論から見た「生協学」 | 若林靖永 |
| ■特集 変革する大学生協 | |
| 大学生協の現状と当面する課題 | 田中 学 |
| 生協を基盤とした新たな文化の創造を | 牛山 積 |
| 地域に根ざした大学づくりと生協への期待 | 住吉広行 |
| 国立大学改革と生協事業の課題 | 和田寿昭 |
| 私立大学と大学生協の事業経営改革 | 福井一徳 |
| 学生の元気が大学の元気,大学生協の元気に! | 新田絵梨 |
| ■研究と調査 | |
| アメリカの社会変革NPO | 岡部一明 |
| ■シリーズ・生協経営を考える① | |
| 商品戦略の課題 | 矢野和博 |
| ■協同の実践 | |
| 地域で支える子育て広場 | 西村一郎 |
| ■自然科学コラム No.37 | |
| 洗剤ゼロの洗濯機をめぐる論争 | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■協同思想の源流を探る No.1 | |
| ロバアト・オウエン | 鈴木 岳 |
| ■経済データを読む No.13 | |
| ペイオフ解禁 | 川名英子 |
| ■研究所を訪ねて No.13 | |
| くらしと協同の研究所 | 山口浩平 |
| 「生活協同組合研究」総目次(2001年4月号~2002年3月号:通巻303~314号) | |
| ■研究所日誌・編集後記 | |