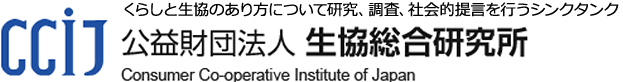- ホーム
- 刊行物情報
- 生活協同組合研究バックナンバー一覧
- 2001年度
生活協同組合研究バックナンバー一覧
2001年度
2002年3月号(Vol.314)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| Too little,too late | 生源寺眞一 |
| ■特集 21世紀の年金制度 | |
| 安心と公正のセーフティネット─ジェンダー視点から年金を考える─ | 大沢真理 |
| 人口構造の変化とわが国の年金制度 | 古郡靹子 |
| ライフスタイルの多様化と今後の年金制度 | 永瀬伸子 |
| 年金財政維持のカギは世代間の合意形成 | 浅羽隆史 |
| 日生協厚生年金基金の現状と課題 | 高木三男 |
| 年金制度に関する国際比較 | 岡田 豊 |
| ■研究と調査 | |
| コープこうべ総合評価の取り組み─2001年版レポートの概要─ | 栗栖 洋 |
| 地域通貨─雇用ジレンマに対するある種の解決策として─ | マルク・S ・ピーコック (翻訳:鈴木 岳) |
| ■協同の実践 | |
| 地域で支える子育て広場 | 西村一郎 |
| ■自然科学コラム No.36 | |
| 炭疽菌とバイオテロ | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■経済データを読む No.12 | |
| 円安 | 川名英子 |
| ■研究所を訪ねて No.12 | |
| コープこうべ・生協研究機構 | 山口浩平 |
| ■文献紹介 | |
| 芝田進午著『実践的唯物論への道─人類生存の哲学を求めて─ | 西村一郎 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2002年2月号(Vol.313)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| プロメテウスとエピメテウス | 関 英昭 |
| ■特集 魅力あるプライベート・ブランドをつくる | |
| 日本の小売業におけるプライベート・ブランド開発の課題 | 新津 重幸 |
| プライベート・ブランドの開発事例から学ぶ | 内藤 清一 |
| コープ商品開発に関する考え方と課題 | 片桐 純平 |
| 21世紀の安心品質Coop ’s 開発の基本的な考え方 | 長野 正 |
| コープ商品の到達点と競争力の課題 | 畑 清志 |
| ■研究と調査 | |
| 食生活の成熟化と今後の変化の方向 | 時子山 ひろみ |
| 生命科学と医療の未来─ヒトゲノム解読の意味と市民的課題─ | 日野 秀逸 |
| テロ事件以後,アメリカの消費者はどう変わったか | デボラ・シュタインホフ (翻訳:河原英夫) |
| ■協同の実践 | |
| 田舎と都市の共生する農めざし─地域協同組合無茶々園の挑戦─ | 西村 一郎 |
| ■自然科学コラム No.35 | |
| 海洋深層水は飲めるか? | 川口 啓明 菊地 昌子 |
| ■経済データを読む No.11 | |
| 経済財政白書 | 川名 英子 |
| ■研究所を訪ねて No.11 | |
| CRI 協同組合総合研究所 | 鈴木 岳 |
| ■文献紹介 | |
| 震災復興市民検証研究会編著 『市民社会をつくる震後KOBE 発アクションプラン 市民活動群像と行動計画』 |
西村 一郎 |
| 編集後記 | |
2002年1月号(Vol.312)
| 生協学に向けて | 蓮見音彦 |
| フードシステム・アプローチとは何か | 生源寺真一 |
| 安全な食品を供給するためにメーカーが取り組んでいること -2000年大規模食中毒事件に学ぶ- |
亀井俊郎 |
| 農と食のリサイクルシステム -生ゴミ・食品廃棄物をめぐって- |
佐藤和憲 |
| 健康・栄養政策からみた生協事業への期待 -「健康日本21」の推進と「新・食生活指針」普及に関連して- |
武見ゆかり |
| 日本の食品産業と生協の商品開発への提起 | 中島正道 |
| パネルディスカッション;フードシステムの考え方を生協事業にどう生かすか | 秋川実・斎藤三郎 阿南久・岩崎登 大木茂・生源寺一 |
| エネルギーの夢を風にのせ -NPO北海道グリーンファンドの市民風車- |
西村一郎 |
| 「環の国」づくりとは? | 川口啓明 菊地昌子 |
| インフレ目標 | 川名英子 |
| 協同総合研究所 | 山口浩平 |
| 全国消費者団体連絡会PLオンブズ会議編 『冷蔵庫が火を噴いた-メーカー敗訴のPL訴訟-』 |
西島秀向 |
| 杉田聡著『クルマを捨てて歩く!』 | 鈴木岳 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
|---|---|
2001年12月号(Vol.311)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 評価の時代 | 川口清史 |
| ■特集 医療生協の未来開発 | |
| 医療生協の中期計画のめざすもの | 大野 博 |
| 盛岡医療生協における保健・医療・福祉のネットワークづくり ─ミニデイサービスと明るいまちづくり─ |
遠藤寿美子 杢屋滋子 高倉四郎 |
| 患者の権利章典の実践 | 尾関俊紀 |
| 医療生協の国際活動 | 高橋泰行 |
| カリフォルニアのエネルギー危機と協同組合の役割 | デボラ・シュタインホフ (翻訳:河原英夫) |
| 市民社会,協同,若返り─国際協同組合研究会議参加報告─ | 山口浩平 |
| 国際NPO 学会アジア地区大会報告 | 栗本 昭 |
| エクセレント制度による職場のパワーアップ ─さいたまコープにみるアルバイトの人事処遇─ |
西村一郎 |
| 食品のリスク・コミュニケーション | 川口啓明 菊地昌子 |
| 環境白書 | 川名英子 |
| さいたま・生協とくらしの研究所 | 西村一郎 |
| 野尻武敏/山崎正和/ハンス・H ・ミュンクナー/ | |
| 田村正勝/鳥越皓之著『現代社会とボランティア』 | |
| 倉部誠著『物語オランダ人』 | |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2001年11月号(Vol.310)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 国立大学の法人化問題その後 | 兵藤 釗 |
| 子育て支援を考える | 福川須美 |
| 子育ては地域で,あらゆる世代が担っていこう ─保育事業の大幅規制緩和と生協の取り組みの可能性─ |
町野美和 |
| ならコープの子育て支援報告─これまでの事,これからの事─ | 植村 徹 |
| のびのび,わくわく。親と子の楽しいひろば─「武蔵野市立0123 はらっぱ」─ | 森下久美子 |
| 活発化するインターネット上の子育てサイトと「ココットネット」の取り組み | 高瀬和哉 |
| ボランティア・マネジメントの理論と実践 | 桜井政成 |
| 学校生協組合員意識調査 | 河原英夫 |
| 子どもたちは小さなまちづくり人─市民と一緒にすすめる埼玉県鶴ヶ島市の教育─ | 西村一郎 |
| 食の安全・安心のエビデンス | 川口啓明 菊地昌子 |
| 女性労働白書 | 川名英子 |
| (財)消費生活研究所 | 西村一郎 |
| 岩垂弘著『生き残れるか,生協─生協トップへの連続インタビュー』 | |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2001年10月号(Vol.309)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 飽食時代の貧しい食生活 | 廣井敏男 |
| ■特集 働き方の変化と生協 | |
| ディーセント・ワーク─今日的課題─ | 堀内光子 |
| 正社員就業の多様化─ジョブ・シェアリングと組織変革─ | 永瀬伸子 |
| インタビュー:ワーカーズ・コレクティブにおける労働を再検討する ─戸別配送を担う「轍」の現状─ |
後藤尚美 |
| NPO ・えんの起業支援と起業の現場をみる | 本間 恵 山口浩平 |
| イギリスにおける2 つの論考から─協同組合VS 株式会社,コープの優位性の再評価─ | 鈴木 岳 |
| ソーシャル・キャピタルの未来─協同組合と社会的企業に関する国際研究会議 参加報告─ | 山口浩平 |
| お酒は体によい? | 川口啓明 菊地昌子 |
| 家計調査 | 川名英子 |
| (財)連合総合生活開発研究所 | 鈴木 岳 |
| 高橋晴雄編著『発想の転換生協─暮らし・仕事・コミュニティ』 | 西村一郎 |
| 山本修・吉田忠・小池恒男編著『協同組合のコーポレート・ガバナンス─危機脱出のためのシステム改革』 | 河原英夫 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2001年9月号(Vol.308)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 小泉「基本方針」は日本を救えるか | 大沢真理 |
| ■特集 自ら学び,考える教育をめざして | |
| 教育改革のめざすもの─21 世紀の学校教育はどのように変わっていくのか─ | 横山英一 |
| 21 世紀の教育の課題 | 汐見稔幸 |
| 生活時間からみた子どもの生活 | 天野晴子 |
| 学校教育と生協の接点─生協ひろしま・コープこうべの実践から─ | 河原英夫 |
| アメリカの多様な教育形態─オルターナティブ・スクールはなぜ拡大してきたか─ | デボラ・シュタインホフ (翻訳:河原英夫) |
| EU における社会的経済の現状 | 北島健一 |
| 中国供銷合作社の運営形態と問題状況─県級供銷社の事例から─ | 青柳 斉 |
| ■自然科学コラム No.30 | |
| 電磁波は有害か? | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■経済データを読む No.6 | |
| GDP 統計 | 川名英子 |
| ■研究所を訪ねて No.6 | |
| (財)協同組合経営研究所 | 鈴木 岳 |
| ■文献紹介 | |
| 横川和夫著『不思議なアトムの子育て──アトム保育所は大人が育つ』 | 西村一郎 |
| 河邑厚徳+グループ現代著『エンデの遺書「根源からお金を問うこと」』 | 鈴木 岳 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2001年8月号(Vol.307)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| ふたたび“生協学”の提唱をめぐって | 藤岡武義 |
| ■特集 共済事業 | |
| 共済事業(協同組合保険)の変遷と現状 | 坂井幸二郎 |
| 保障と矛盾の集中としての共済事業──求められる協同組合保険論の復権 | 本間照光 |
| 地域生協の共済事業の現状と課題 | 大友弘巳 |
| 大学生協の共済事業 | 佐藤 孝 |
| 全労済の共済事業 ─全労済21 世紀ビジョン第2 期計画にもとづく活動展開─ |
阿部晃司 |
| 12 万人のたすけあいの意味するもの─ちばコープ | 小島泰宣 |
| ■研究と調査 | |
| 京都府内農業振興をめざす新たな試み ─「食料・農業・農村基本法」と京都府生産・消費連携推進協議会─ |
尾松数憲 |
| 食用植物油の利用実態調査 | 日本生協連くらしと商品研究室 |
| ■協同の実践 | |
| まちの未来は自分たちの手で─「みたか市民プラン21 会議」の取り組み─ | 西村一郎 |
| ■自然科学コラム No.29 | |
| 「環境にやさしい」は本当か? | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■経済データを読む No.5 | |
| 内外価格差の動向 | 川名英子 |
| ■研究所を訪ねて No.5 | |
| 農林中金総合研究所 | 山口浩平 |
| ■文献紹介 | |
| 高橋勇悦・和田修一編『生きがいの社会学─高齢社会における幸福とは何か』 |
河原英夫 |
| 伊藤セツ・天野寛子・李基栄共編著 『生活時間と生活意識─東京・ソウルのサラリーマン夫妻の調査から』 |
近本聡子 |
| 財団法人 生協総合研究所 理事会報告 | |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2001年7月号(Vol.306)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「生協学」という提言をめぐって─計画・夢・そして現実─ | 宮坂富之助 |
| ■特集 生協産直の再確立のために | |
| 青果物フードシステムの現状と課題 | 佐藤和憲 |
| 日本生協連 2001 年度版農産・産直基準の提案 | 小野勝一郎 |
| わがJA の地域農業振興計画の実践 | 黒澤賢治 |
| 東海コープ事業連合における産消提携の改革 | 中島悦朗 |
| 生鮮青果センターの改善の取り組み | 竹山孝二 |
| 産地情報管理とIT 技術の活用 ─首都圏コープ事業連合の産直政策とFarmers.net ─ |
野村和夫 |
| ■研究と調査 | |
| 福祉用具の利用状況と今後の課題 ─介護・福祉用具に関する消費者の意識調査結果について─ |
笹野武則 |
| サンタ・バーバラのボランティア─高齢者にどう役立つか─ | デボラ・シュタインホフ 翻訳:栗本 昭・石塚秀雄 |
| ■自然科学コラム No.28 | |
| 狂牛病の広がり | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■経済データを読む No.4 | |
| 春闘 | 川名英子 |
| ■研究所を訪ねて No.4 | |
| 株式会社 イズミヤ総研 | 山口浩平 |
| ■文献紹介 | |
| 西村 貢・中井健一・黒田学編著『生協と住みよいまちづくり─コープぎふの発信』 | 鈴木 岳 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2001年6月号(Vol.305)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 自然な人間的生活感覚を回復しよう | 田中 学 |
| ■特集 インターネットとくらし | |
| マーケティングからみたインターネット販売(B2C ) | 上田隆穂 |
| インターネットの拡大と生活者への影響 ─日本型IT 環境とパッシブ・アクティブな活用が及ぼす影響─ |
若原圭子 |
| サイバーコミュニティのツールとしての,Web 日記と掲示板 | 山下清美 |
| インフォテック対インフォアーツ ─インターネット関連言説における構図転換のための試論─ |
野村一夫 |
| インターネットと生協組合員 | 近本聡子 |
| イギリス生協の未来開発の見取り図 ─生協のあり方検討会報告書の経過と内容─ |
栗本 昭 |
| 世界中にさわやかな風のような平和を─ピースウィンズ・ジャパンの取り組み─ | 西村一郎 |
| 始まった遺伝子組み換え表示─その2 | 川口啓明 菊地昌子 |
| 有効求人倍率 | 川名英子 |
| 市民セクター政策機構 | 山口浩平 |
| 西條節子著『高齢者グループリビング[COCO 湘南台]』 | 西村一郎 |
| 村城正著 『どうする! 高齢社会日本─「介護保険」で,あなたの老後は本当に安心か』 |
河原英夫 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2001年5月号(Vol.304)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| ILO と協同組合 | 中川雄一郎 |
| ■特集 仕事と家族生活の組み立て: | |
| 「ファミリー・フレンドリー企業」を目指して | 佐藤博樹 |
| 「生協で働く女性・男性職員のくらし方と働き方調査」について | 竹内敬子 |
| インタビュー:育児に参画する男性・女性のネットワーク | 田中幹大 |
| ■研究と調査 | |
| 「生活創造」時代における生活研究のフロンティア | 御船美智子 |
| 21世紀を迎えたエコノミー・ソシアルと協同組合の課題について ─RECMA 誌特集号の論稿から─ |
鈴木 岳 |
| 福祉に関する組合員活動の形態に関する論考 ─1980 年代以降の組合員活動をふまえて─ |
山口浩平 |
| ■協同の実践 | |
| 協同の力で子どもとの対話─NPO 文化学習協同ネットワークの取り組み─ | 西村一郎 |
| ■自然科学コラム No.26 | |
| 始まった遺伝子組み換え表示 | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■経済データを読む No.2 | |
| 年金 | 川名英子 |
| ■研究所を訪ねて No.2 | |
| セゾン総合研究所 | 近本聡子 |
| ■文献紹介 | |
| G ・エスピン- アンデルセン著(渡辺雅男・渡辺景子訳) 『ポスト工業経済の社会的基礎─市場・福祉国家・家族の政治経済学─』 |
宮本太郎 |
| 広井良典著『ケア学─越境するケアへ』 | 山口浩平 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |
2001年4月号(Vol.303)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 供給過剰時代の生協 | 野村秀和 |
| ■特集 | |
| ボランティアのきりひらく21世紀の市民社会 | 妻鹿ふみこ |
| ボランティア活動を支える心理─インセンティブを中心に考える─ | 田尾雅夫 |
| 日本におけるボランティア国際年の取り組み | 村上徹也 |
| 愛と協同のボランティア─コープこうべにおける取り組み─ | 山添令子 |
| みやぎ生協のボランティア活動 | 佐藤修司 |
| ■研究と調査 | |
| コミュニティ形成におけるインターネットの役割 | デボラ・シュタインホフ |
| ■協同の実践 | |
| 被災地責任の普遍化を─神戸における被災地NGO 恊働センターの取り組み─ | 西村一郎 |
| ■自然科学コラムNo.25 | |
| 厚生労働省の食品安全対策 | 川口啓明 菊地昌子 |
| ■経済データをよむNo.1 | |
| 2001 年度予算案をみる | 川名英子 |
| ■研究所を訪ねてNo.1 | |
| 社団法人生活経済政策研究所 | 河原英夫 |
| ■文献紹介 | |
| 長谷川勉著『協同組織金融の形成と動態』 | 平石裕一 |
| 芹沢茂登子著『ステロイド漬けの日々と骨粗鬆症』 | 平石裕一 |
| ■研究所日誌・編集後記 | |