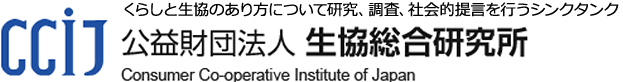刊行物
生協総研レポートNo.102 生協共済研究会 2019年度~2024年度の歩み
※刊行後1年未満の刊行物のJ-STAGEでの閲覧は、生協総合研究所会員の方に限らせていただきます。
是非、当研究所の会員にご加入ください。個人会員加入のお申込はこちら 団体会員につきましてはお問合せください
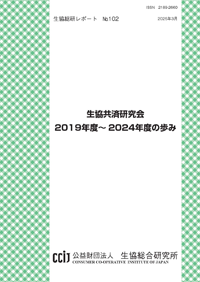
2025年国際協同組合年(IYC2025)の記念すべき年に、「生協共済研究会2019年度~2024年の歩み」(生協総研レポート)を発行することができた。世界各地でIYC2025に関連するさまざまなイベントが行われているなかで、研究会としてささやかな貢献ができたとすれば、望外の喜びである。
生協共済研究会の活動報告書は、2016年、2019年に続き、今回で3回目である。初回の「10年間の歩み」のまえがきを読み返すと、「10年後研究会が続いている保証はないが、そうあってほしい」と記述していた。関係各位の厚い支援に支えられて、無事継続できそうである。この場を借りて心からお礼を申し上げる。
今回は多様なテーマの14の論文等が寄稿された。研究の多様性が研究会の継続を後押ししたことも見逃せない。もっとも、これらの研究の底流には共済と保険の異同、生協共済の独自性などに対する問いが感じられる。ガバナンスなどの制度面の違いは明確であっても、事業面の違いは縮小している。それにもかかわらず、生協共済の存在意義を探究する真摯な研究姿勢に敬意を表したい。
以下、共済と保険の異同について私見を申し述べる。共済研究の初期において、共済団体も保険の仕組みや技術を用いて保障事業を行っているため、両者の違いは協同組合と株式会社・相互会社との違いに存在すると考えていた。そして、協同組合保険と会社保険を統括する保険の概念とは一体どのようなものなのかについて関心を持った。もっとも、共済は協同組合だけでなく、社会保険や企業の福利厚生などにおいて広く使用されている。やがてそれらを包括するような体系化をしたいと考えるようになった。
その結果、リスクの移転と分散の機能面から保険を把握し、共同体、市場および政府(国)の経済組織において、それぞれ保険が提供されていると整理した。先進国においては、保険市場と社会保険と比べて共同体の「保険」(非公式の保険)の存在は小さいものの、これらが未発達の途上国においては、共同体の「保険」がなお重要な役割を果たしている。また、提供される保険はそれぞれの経済組織の原理、すなわち互酬(共同体)、交換(市場)および再分配(政府)に従う。
アソシエーション組織である協同組合は、共同体、市場および政府の中間領域に存在し、営利企業でも公営企業でもない民間・非営利企業である。協同組合共済は、「相互扶助」と「協同」の経済原理に従い、「保険」(保障)を提供する。ただし、中間領域であるがゆえ、ポジショニングによっては、他の経済組織の原理の影響を受ける。生協共済は現在どのような場所に存在するのだろうか。
中間領域はサードセクター、非営利セクターまたは社会連帯経済として知られる。国連は社会開発における協同組合の貢献や役割を高く評価し、2012年に続く2度目の国際協同組合年を迎えた。生協共済がよりよい社会を目指してさらに躍進することを願っている。
主な目次
刊行にあたって(岡田 太)
協同組合共済の非営利性に関する一考察(岡田 太)
共済と保険の相違──機能論的アプローチによる分析──(米山 高生)
自動運転をめぐる補償の在り方:ELSIとしての検討(中林 真理子)
低所得世帯におけるリスクへの備えと共済の意義(大塚 忠義)
共済事業における健康経営の役割と可能性(恩藏 三穂)
日本における共済の存在理由と可能性(宮地 朋果)
生協共済のガバナンス再論:全労済とコープ共済連の分析(栗本 昭)
プロテクションギャップの現状と課題(崔 桓碩)
災害時のリーガル・ニーズ(千々松 愛子)
長寿リスクの経済的保障と生活設計(根本 篤司)
わが国における協同組織金融機関の現状と課題──信用金庫を中心に──(谷川 孝美)
災害補償に関する制度には “たすけあい” の精神がどのように内包されているのか
──国会議事録を用いて──(吉田 朗)
全国生協組合員調査 共済・保険に関する設問の分析報告(西尾 由)
国際協同組合保険連合(ICMIF)2024年大会 参加報告(西尾 由)
生協共済研究会2019年度~2024年度の活動記録
お申込み・お問合せ
公益財団法人生協総合研究所(茂木、鷲見、西尾)
TEL:03-5216-6025 E-mail:ccij@jccu.coop