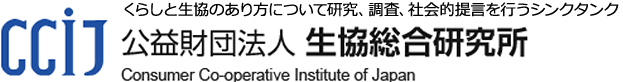刊行物
生活協同組合研究 2025年11月号 Vol.598
※刊行後1年未満の刊行物のJ-STAGEでの閲覧は、生協総合研究所会員の方に限らせていただきます。
是非、当研究所の会員にご加入ください。個人会員加入のお申込はこちら 団体会員につきましてはお問合せください。
「余暇」を考える

「余暇」という言葉は余った暇という文字で書かれるが,余った時間などではなく,その過ごし方が自分の生きがいや,生きる目的となっている場合も少なくない。また,この消費者の余暇時間をめぐって,観光産業や娯楽業だけではなく多くの産業が奪い合いをしているような状況である。生協でいえば,組織運営に関わる活動や組合員活動などの部分で,この余暇の奪い合いに参加しているといえるだろう。実際に,アンケートなどをとり,組合員活動に参加しない理由などを組合員に尋ねると,「時間がないから」という回答が相当の割合を占める。「時間がないから」という理由も,その内実は「本当に時間が無くて,参加したいけど参加できない」場合もあるだろうし,「他にやりたいことがあるので,そちらを優先したい」という場合もあるだろう。
余暇は消費者本人にとっても,消費者を取り囲む様々な取り組み・サービスにおいても非常に貴重な資源となっており,生協の組織運営に関わる活動や組合員活動もその余暇を費やしてもらう取り組みであることから,消費者の余暇の現状について十分に把握する必要がある。この問題意識が特集の出発点となっている。
具体的な余暇時間の定義は難しいが,近い概念として社会生活基本調査における3次活動の定義が用いられることが多い(表1)。生理的に必要な活動を1次活動,仕事・家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動を2次活動,これら以外で各人の自由に使える時間における活動を3次活動として分類している。
1次活動や2次活動においても,生協の事業や取り組みに関係する活動は多くあるが,その多くで時短や利便性が求められるようになっており,いかに1次活動や2次活動の時間を節約し,3次活動の時間を確保していくかが消費者の関心事になっているといえよう。そうした中で,育児や介護による負担は3次活動の時間を大きく減少させる要因ともなっており,少子化や介護鬱うつといった社会的な課題にもつながっている。ワークライフバランスという考え方も3次活動の確保と強く関連した考え方だろう。
そもそも人の持つ時間は,命とほぼ同義であり,自分の限られた時間を最大限活かしたいという欲求はごく自然なものである。価値観が多様化し,仕事や結婚を含めた生き方そのものが自由になっていく中で,仕事や子育て以外の部分に生きがいを見出す人も多くなった。その結果が,現在の余暇を,言い換えれば自分の時間を大事にしたいという現在の消費者の意識につながっているものと筆者は考えている。
表1 社会生活基本調査における1次・2次・3次活動の例
| 1次活動 | 睡眠,身の回りの用事,食事 |
| 2次活動 | 通勤・通学,仕事,学業,家事,介護・看護,育児,買い物 |
| 3次活動 | 移動(通勤・通学を除く),テレビ・ラジオ・新聞・雑誌,休養・くつろぎ 学習・自己啓発・訓練(学業以外),趣味・娯楽,スポーツ ボランティア活動・社会参加活動・交際・付き合い,受診・療養,その他 |
また,余暇は今後よりいっそう進む高齢化社会を考えても重要な要素となる。退職後や子どもの独立後,増えた自分の時間をどう使うかは高齢者の心身的な健康に大きく影響する。活動範囲が狭まることによる運動不足はフレイルや筋力低下につながり,社会とのネットワークが途切れ,孤立してしまうといった問題に直面する高齢者は少なくない。高齢者が老後の余暇時間を上手く活用し,自身の心身的健康を保てるような環境を整えることも重要な課題といえるだろう。
ここまで示してきたように,余暇は本人の幸せだけではなく,様々な事業体の事業・サービス・取り組みに大きく関連し,日本の社会的課題とも密接に関係している。生協にとっても無関係ではなく,まずは日本社会における余暇の現状について本特集で確認していきたい。
平井稿では社会生活基本調査のデータを使用して,日本人の余暇時間と属性や経済的資源(年齢・性別・最終学歴・職業・世帯年収)の関係を分析している。また,余暇時間を休息型,趣味型,交遊型に分類し,それぞれの配分についても注目している。基本的な余暇時間の現状を捉える上で非常に参考になる内容となっている。
長田稿ではより具体的に余暇活動の内容や,余暇活動における意識について注目し,行動と意識の両面から多角的に分析を行っている。日本社会において余暇重視派が多数派になったことや,余暇行動において「外出型」の力強い回復と,定着した「在宅・デジタル型」が共存するハイブリッドなスタイルが広がっていることなどを指摘している。
三浦・原・黒木稿では都市部に暮らす就労・子育て世帯を対象とした「時間貧困」に関する調査の結果を紹介している。日本国内では時間貧困はその定義や尺度が確立されておらず,その現状を十分に検討することができていなかった。そこで,主観的時間貧困に関する尺度を開発し,その妥当性を検証するとともに睡眠時間,余暇時間,幸福感,仕事の満足感との関連を分析している。
相田・増子稿では高齢者の健康や幸福と余暇活動の関連を分析している。余暇活動を行っていない群と,新たに余暇活動を開始した群の群間比較を行い,余暇活動を新たに開始することでその後6年間における死亡および要介護リスクが低下することを示した。また,高齢者になる前の段階での,仕事の忙しさとそれによる余暇活動を行う時間や心の余裕の少なさに課題があることも指摘している。
真鍋稿では余暇時間と効率化を目指す行動意識との関連を分析している。その中で,余暇時間と効率化行動における意識にはジェンダーによる違いがあり,女性の場合は余暇時間が長くなるほど効率化行動が減少するのに対し,男性の場合は余暇時間が短い場合と長い場合に効率化行動が減少するといった傾向の違いを指摘している。
「余暇」について真剣に検討することは機会としてはあまり多くないものと思われるが,本特集をきっかけに改めて考えてみていただきたい。
(宮﨑 達郎)
主な執筆者:平井太規,長田 亮,三浦 武,原 広司,黒木 淳,相田 潤,増子紗代,真鍋公希
目次
- ●巻頭言
- 被爆・戦後81年を私たちはどう迎えるか(秋山 純)
- ●特集 「余暇」を考える
- 生活時間データでみる3次活動の実態──2016年の余暇時間──(平井太規)
- 日本の余暇活動の現状と動向──レジャー白書からみたポストコロナ時代の余暇の過ごし方──(長田 亮)
- 仕事と家事を両立する世代の時間貧困(三浦 武・原 広司・黒木 淳)
- 余暇活動と高齢者の健康(相田 潤・増子紗代)
- 余暇時間と効率化行動の関連はジェンダー間で異なるのか(真鍋公希)
- ●IYC2025の機会に協同組合の価値を再考する(第8回)
- 青森県民生協の長距離お買い物無料ミニバス・三厩ルート(鈴木 岳)
- ●国際協同組合運動史(第44回)
- 1972年第25回ワルシャワICA大会(鈴木 岳)
- ●本誌特集を読んで(2025・9)
- (山口郁子・亀田篤子)
- ●研究所日誌
- ●全国研究集会「超高齢社会において生協が果たすべき役割を考える」(11/21)
- ●2025年度生協総研賞 第15回表彰事業受賞式のご案内
- ●2025年度生協総研賞・第23回助成事業対象者決定のお知らせ