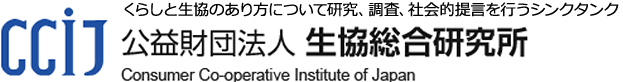刊行物
生活協同組合研究 2025年10月号 Vol.597
※刊行後1年未満の刊行物のJ-STAGEでの閲覧は、生協総合研究所会員の方に限らせていただきます。
是非、当研究所の会員にご加入ください。個人会員加入のお申込はこちら 団体会員につきましてはお問合せください。
超高齢社会における介護の行方

2025年10月時点において、団塊世代が揃って75歳以上の後期高齢者となり、団塊ジュニア世代がおおむね50歳を迎えている。少子高齢社会を反映して人手不足があらゆる業種で取り沙汰されるようになってきた。介護業界ではとりわけ人手不足が深刻化している。
さて今号特集では「超高齢社会における介護の行方」をテーマとした。岩波新書『介護格差』を著している結城氏は、特に訪問介護においては有効求人倍率が実に14倍に達していることに触れ、「制度あってサービスなし」といった状況に対する警鐘を鳴らしている。そのような中で将来において介護サービスを利用するためにどのような準備をしておくべきかを解説いただいた。
立命館大学名誉教授の津止氏には、今後ますます増えていくであろう“仕事と介護の両立”を求められる“ワーキングケアラー”について論述いただいた。同氏によればワーキングケアラーの約9割は仕事と介護の両立に不安を抱えており、うち半数は「自身の心身の健康を害する」ことが恐れるレベルとのことである。
日本総合研究所の紀伊氏には、様々な創意工夫によって人手不足を解消しつつある先進的な介護事業者の取り組みについて丹念にご紹介いただいた。貴重な最新情報が惜しみなく詰まっており、全国の生協の福祉事業においても参考にして活用できる内容があることを願う。
介護事業を展開する中で、要介護者のみならずその家族にも心を砕いているのが福井県民生協である。福祉事業を統括する蓬莱谷氏によれば同生協の福祉事業では「たとえ認知症であっても利用者本人の想いや願いを理解し、誰もが自分らしいくらしを継続できるように支えるケアを実践する」ことを大切にしているとのことである。介護事業の利用者本人に寄り添うことはもとより、要介護者を抱える家族にも心を寄せて展開したのが「小規模多機能型居宅介護」であろう。
全国コープ福祉事業連帯機構の梅津事務局長と野村氏には「生協の福祉事業の現状と課題・将来展望」をテーマに話を聞いた。コープ福祉機構は設立から4年目を迎えているが、福祉事業に取り組む生協間の実践ノウハウの交流促進に大いに貢献していることが分かった。今後の生協による福祉事業の発展にますます寄与していくことであろう。
今般の介護特集が生協の役職員が福祉事業の将来について考えるヒントになれば幸甚に思う。
(西尾 由)
主な執筆者:結城康博、津止正敏、紀伊信之、蓬莱谷修久、梅津寛子、野村文亮
目次
- ●巻頭言
- 新しい価値とライフスタイルに挑む若者たちの活動(宮本みち子)
- ●特集 超高齢社会における介護の行方
- 介護格差の克服に向けて──介活のススメ──(結城康博)
- 仕事と介護の両立支援の政策的課題──介護のある暮らしを社会の標準に──(津止正敏)
- 介護人材不足への対応策──働き手から選ばれる介護事業経営──(紀伊信之)
- 福井県民生協の福祉事業──利用者本人の想いや願いを大切に──(蓬莱谷修久)
- 生協の福祉事業の現状と課題・将来展望(梅津寛子・野村文亮)
- ●IYC2025の機会に協同組合の価値を再考する(第7回)
- 福井県民生協の「くらしのサポート」──“ゆりかごから墓場まで”を実践──(中川政弘(聞き手:西尾 由))
- ●国際協同組合運動史(第43回)
- 1969年第24回ハンブルクICA大会②(鈴木 岳)
- ●本誌特集を読んで(2025・8)
- (高田公喜・百瀬紋乃)
- ●研究所日誌
- ●全国研究集会「超高齢社会において生協が果たすべき役割を考える」(11/21)
- ●アジア生協協力基金2026年度・助成金一般公募のご案内
- ●2025年度生協総研賞第15回「表彰事業」受賞作が決定しました