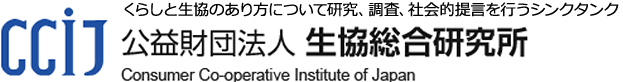刊行物
生活協同組合研究 2025年9月号 Vol.596
※刊行後1年未満の刊行物のJ-STAGEでの閲覧は、生協総合研究所会員の方に限らせていただきます。
是非、当研究所の会員にご加入ください。個人会員加入のお申込はこちら 団体会員につきましてはお問合せください。
労働運動と協同組合

労働運動は古くからある社会運動の代表的な存在であり、協同組合、とりわけ生協運動とも様々な形で連携して活動してきた。とりわけ、労働者自主福祉運動、あるいは単に労働者福祉運動といわれる労働者が自ら、自分たちの福祉をつくりだそうとする運動のなかからは協同組合の運動も多く生まれている。労働金庫やこくみん共済coop(全労済)などは、この労働者福祉運動のなかから生まれ発展してきた代表的な協同組合である。労働者福祉運動の中心的存在である労働者福祉協議会(労福協)は、そうした労働運動と協同組合運動の結節点としてその役割をはたしてきた。
近年、生協運動のなかで他団体との連携は重要なトピックとなっているが、そこで中心となっているのは各種協同組合間の協同や自治体、市民活動組織との連携である。そのことの意義は強調されこそすれ、否定されるようなものでないことはいうまでもないが、ルーツや運動の方向性を考えれば労働運動との関係についても、もっと深められてよいはずである。実際には、労福協などを媒介としながら奨学金問題の取り組みやフードバンク活動などの実践が進められているが、生協運動と労働運動の間で相互が意識されることはあまり多くないようにも感じられる。
そこで、本特集では労働運動と生協をはじめとする協同組合の関係に焦点を当て、労働者福祉運動の意義を再確認しつつ(中村稿)、その歩みを振り返るとともに(高橋稿、篠田稿)、労福協の現況や具体的な実践、展望や課題などを紹介し(日詰稿、麻生稿、南部インタビュー)、社会的連帯経済などの現代的なテーマの中における立ち位置を検証する(伊丹稿)。
生協は日本最大の市民団体としばしば指摘されるが、いまや3000万人を超える組合員の生活を支える巨大な組織となった。他方、労働運動は戦後の日本社会の中で大きな役割をはたしてきた組織であり、政治や経済など、社会の中の様々な側面で大きな影響力を持つ。中央のみならず、それぞれの地域で両者の連携が深まることによって、私たちがくらし、働く社会をより良くしていく大きな力が生まれることは疑いえない。
本特集がそうした連携をうみだし、深めていく一助となれば幸いである。
(三浦一浩)
主な執筆者:中村圭介、南部美智代、三浦一浩、高橋 均、日詰一幸、麻生裕子、伊丹謙太郎、篠田 徹
目次
- ●巻頭言
- ILO100号条約の不審な政府公定訳(遠藤公嗣)
- ●特集 労働運動と協同組合
- 連帯社会の要としての労働者福祉協議会(中村圭介)
- インタビュー:労働者福祉運動の展望と課題(南部美智代(聞き手:三浦一浩))
- 協同組合と労働組合の関係性の歴史とこれから(高橋 均)
- 労働者自主福祉運動と社会的課題への対応──静岡県労福協が紡ぎ出す地域社会とのかかわりの形──(日詰一幸)
- 地域における労福協の組織と活動(麻生裕子)
- 社会的連帯経済から考える労働運動と協同組合運動(伊丹謙太郎)
- 労働運動と協同組合運動のグローバル・ヒストリー事始め──賀川豊彦が百歳まで生きていたなら──(篠田 徹)
- ●研究と調査
- 消費者は「エシカル消費」をどのように捉えているのか(宮﨑達郎)
- ●IYC2025の機会に協同組合の価値を再考する(第6回)
- コープさっぽろの高齢者向け取り組みについて(外川雅喜・栗栖重明・岩本啓祐・(聞き手:西尾 由))
- ●国際協同組合運動史(第42回)
- 1969年第24回ハンブルクICA大会①(鈴木 岳)
- ●本誌特集を読んで(2025・7)
- (前田和記・林 薫平)
- ●新刊紹介
- 松尾隆佑・源島穣・大和田悠太・井上睦編著『インフォーマルな政治の探究』(三浦一浩)
- ●研究所日誌
- ●公開研究会「アジア生協協力基金 活動報告会」(9/19)
- ●アジア生協協力基金2026年度・助成金一般公募のご案内
- ●全国研究集会「超高齢社会において生協が果たすべき役割を考える」(11/21)