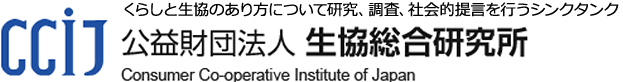刊行物
生活協同組合研究 2025年8月号 Vol.595
※刊行後1年未満の刊行物のJ-STAGEでの閲覧は、生協総合研究所会員の方に限らせていただきます。
是非、当研究所の会員にご加入ください。個人会員加入のお申込はこちら 団体会員につきましてはお問合せください。
社会的課題解決に取り組む次世代リーダーたち

本号の特集を組むにあたっては、これまで仕事の中で考える機会のあった、系統のやや異なる複数のトピックがベースになっている。一つは日本社会の少子高齢化であり、営利・非営利を問わず多くの組織が後継者不足のため事業の将来(継続)に不安を抱えている、と言われていること(ここには事業を継続してくれる次世代をどう確保するかという関心も含まれる)。そしてもう一つは、人口が減少する中で、むしろ増えているようにさえ感じられる社会的課題(貧困、孤立等個人では解決困難な問題)に、社会の中の様々なアクターはどう取り組んだら良いのか、ということ。さらには社会的課題の解決には当然お金がかかるのであり、特に中央・地方政府の財政赤字が蓄積する中でどのようにリソースを集めるのか、ということがあった。またこれらの問題に関連して、「失われた30年」と言われる厳しい経済状況の下で、お金にならないと一般的に考えられる社会的課題解決に取り組もうとする人々(個人)は一体どのような人たちなのか、あるいは特段知識やスキルを持たない普通の人が集まってそのような活動の組織を立ち上げ、運営するにはどうしたら良いか、といったことである。これらの多方面にわたる問題の関係について、自分の中ではいまだに理論的な整理が明確にできていないが、これらの問題はいずれも少しずつつながっているように感じている。
そこで本号の特集ではまず、「お金にならない」と避けられがちな社会的課題の解決にあえて取り組む、(多くの組織が喉から手が出るほど欲しがっている)若いリーダーの方たちに、なぜそのような活動に取り組んでいるのか、お金の問題も含めて活動の中の苦労や喜びといったことについて執筆下さるよう依頼した。地域福祉(濱野論稿)、若者の政治参加(足立論稿)、社会保障へのアクセス支援(横山論稿)、大学生活の中の社会活動(戸張論稿)と活動の分野は異なるが、それぞれの著者がどのようなきっかけで活動に関与するようになったか、またこれらの活動の魅力(と苦労)について誠実な、生き生きとした言葉でつづって下さっている。
そしてこれらの実践を研究の面から捉えることを目的に2名の専門家から寄稿を頂いた。鎌田氏の論稿では社会的課題解決に取り組む手法としてコミュニティ・オーガナイジングについて紹介を頂き、西出氏には特に若いリーダーを社会として促進する可能性に関する研究を紹介する原稿を頂いた。
本号の特集を通じて、経済の停滞や少子高齢化の続く中でも社会的課題解決のために行動する若い人々の存在が改めて認識され、彼らの周りに(世代に関わらず)彼らを応援したい人たちが集まることになれば嬉しいと思う。
(山崎 由希子)
主な執筆者:濱野将行、足立あゆみ、横山北斗、戸張 桜、鎌田華乃子、西出優子
目次
- ●巻頭言
- いっそ女性総理を!? ──男女雇用機会均等法から40年──(岩田三代)
- ●特集 社会的課題解決に取り組む次世代リーダーたち
- 不登校・精神障害・ひきこもり・虐待。さまざまな背景を持つ若者が,楽しみながら多くの人を救い,救われ続ける「ごちゃまぜ地域」の未来(濱野将行)
- 若い世代が声をあげ,その声が響く社会をつくるために(足立あゆみ)
- 制度はあるのに,なぜ届かないのか ──日本の社会保障制度が抱える構造的課題への実践──(横山北斗)
- 社会課題を“自分ごと”に変える,生協学生委員会の力(戸張 桜)
- どのように行動すると社会は変わるのか? ──コミュニティ・オーガナイジングの視点から考える──(鎌田華乃子)
- 社会を変える若手リーダー(=社会イノベーター)を地域や社会で促進するためには(西出優子)
- ●IYC2025の機会に協同組合の価値を再考する(第5回)
- 近隣組織と協力して子どもの成長を支援する出雲医療生活協同組合「学VIVA」(山崎由希子)
- ●国際協同組合運動史(第41回)
- 1966年第23回ウィーンICA大会②(鈴木 岳)
- ●本誌特集を読んで(2025・6)
- (加瀬和美・石井勇人)
- ●新刊紹介
- 岩田正美著『私たちの社会福祉は可能か』(山崎由希子)
- ●研究所日誌
- ●公開研究会「証言による戦時下と敗戦後のくらし」(8/27)
- ●公開研究会「アジア生協協力基金 活動報告会」(9/19)
- ●全国研究集会「超高齢社会において生協が果たすべき役割を考える」(11/21)
- ●アジア生協協力基金2026年度・助成金一般公募のご案内