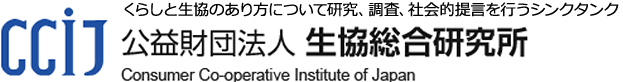刊行物
生活協同組合研究 2025年7月号 Vol.594
※刊行後1年未満の刊行物のJ-STAGEでの閲覧は、生協総合研究所会員の方に限らせていただきます。
是非、当研究所の会員にご加入ください。個人会員加入のお申込はこちら 団体会員につきましてはお問合せください。
どうなる、日本のコメ

少し前までは、コメだけは日本でおおよそ自給でき、価格も安定している「物価の優等生」と一般的には認識されていたように思う。しかし昨年夏以来、コメの値上がりが止まることなく、どのような事態が起こっているのか、生産と流通の状況は、また過去の振り返りと将来は、などという関心から久々のコメ特集とあいなった。
これを企画し、執筆者の方々に依頼申し上げた頃、既にコメの値段は高騰を続け、日々のニュースとなっていた。しかしその後、農林水産大臣が交代し、日々状況が変化し、コメと大臣をめぐってメディア報道が劇的に過熱するという思いがけない事態となった。このような情勢の転変するなかのご執筆となり、大変心苦しい状況となってしまった。が、このなかでもご寄稿をいただいたことに、まずは御礼を申し上げたい。5つの論考には、日本のコメについてそれぞれ専門的な論点からの沈着な見解・分析が存分に示されている。必ずや読者にとって、示唆に富む内容と思う。
なお、このコメ高騰の影響は、主食としてももちろんであるが、国産米を使用する煎餅や菓子などの各種加工品や、日本酒・焼酎製造、ひいてはもち米からつくられる餅などにも、これからより一層の波及が懸念される。このような視点からも今後とも注視したい。
(鈴木 岳)
主な執筆者:中嶋康博、生源寺眞一、小池(相原)晴伴、小川真如、大木 茂
目次
- ●巻頭言
- 「営利」・「非営利」と社会的課題(中島智人)
- ●特集 どうなる,日本のコメ
- 米価格高騰の背景──米流通制度改革への示唆──(中嶋康博)
- 米をめぐる消費と生産を振り返る:令和の米騒動を契機に(生源寺眞一)
- 北海道産米の歴史と昨今の状況(小池(相原)晴伴)
- ポスト生産調整・ポスト減反に向けて必要な視座(小川真如)
- 生協産直・事業におけるコメ──事業上の困難と活動上の重要性──(大木 茂)
- ●IYC2025の機会に協同組合の価値を再考する(第4回)
- アジアで活躍する非営利組織・市民組織による組織作りの価値──アジア生協協力基金 一般公募助成事業の成果より──(宮﨑達郎)
- ●国際協同組合運動史(第40回)
- 1963年ICA大会②~ 1966年第23回ウィーンICA大会──新原則をめぐって──(鈴木 岳)
- ●本誌特集を読んで(2025・5)
- (梅津寛子・五十嵐雄悟・生田園深)
- ●研究所日誌
- ●生協総研賞「第23回助成事業」の応募要領(抄)
- ●全国研究集会「超高齢社会において生協が果たすべき役割を考える」(11/21)