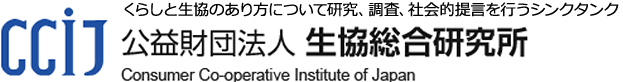刊行物
生活協同組合研究 2025年4月号 Vol.591
※刊行後1年未満の刊行物のJ-STAGEでの閲覧は、生協総合研究所会員の方に限らせていただきます。
是非、当研究所の会員にご加入ください。個人会員加入のお申込はこちら 団体会員につきましてはお問合せください。
日本の大学の学費・奨学金問題を考える

「日本・ルワンダ・マダガスカル」、この3国の共通点をご存じだろうか?
2007年当時、「国際人権規約」を批准していた164か国のうち、同規約13条2項の「中等・高等教育漸進的無償化条項」を留保していた3国である。2008年にルワンダが留保を撤回し、日本は危うく高校・大学等の学費無償化条項を留保する唯一の国になるところだったが、2012年に日本政府もこの条項の留保を撤回した。この時点から高校・大学等の学費無償化は国際的な公約になり、国連機関からも審査を受けることとなった。
1970年代から急上昇した大学4年間の学費は、多くの国立大学で約240万円、私立大学の平均は約470万円と国際的にみても非常に高額となっている。2017年に給付型奨学金が創設、2020年には修学支援新制度も開始、2024年の総選挙でほとんどの政党・議員が「高等教育無償化」を公約に掲げて当選し、衆議院の過半数を占め、私立を含めた高校授業料無償化も決定する見通しだ。一方で、東京大学や多くの私立大学で2025年度の学費値上げを実施するなど無償化に逆行する動きもあって、現状は非常に混沌としている。
このような状況を踏まえ、本特集では計8本の論稿・コラムを収録して、この問題の理解を深めたいと考えた。大内論稿では、この問題のアウトラインを整理いただき、大内氏が中央労福協とともに取り組んでいる高等教育費負担軽減に向けての取り組みを紹介いただいた。本田論稿では、大学教育の社会的存在価値である「エクセレンス(優秀さ)」「イークオリティ(機会均等)」「アクセス(規模の確保)」の三つがいずれも機能不全状態にあることを、歴史的経緯を含めて解説いただいた。矢野論稿では、家族と会社によって支えられてきた日本の大学教育が学費の「親負担主義」の限界によって崩壊しつつある現在、社会(政府)の投資が求められることを訴えられた。小林論稿では、2020年度より導入された「修学支援制度」の目的が「教育の機会均等」ではなく「少子化対策」となっているというねじれや急ごしらえの制度設計等による問題点と今後の課題について解説いただいた。学費・奨学金問題の根本的な解決には文教予算増額が議論になるが、その中で「大学の定員割れや供給過剰」が話題に上ることが多い。河村論稿では、この「大学の供給過剰問題」への対応について、文科省の審議会での検討内容を踏まえ問題提起していただいた。
岩重コラムでは、奨学金返済の相談・救済の現場から見えてくる問題点と改善の方向性について解説いただいた。福島コラムでは、コープさっぽろが取り組む独自の奨学金制度の概要とこれまでの成果について紹介いただいた。コープさっぽろ以外にもコープみらいやコープこうべ、パルシステムグループなどをはじめ、多くの生協で組合員の募金等を財源にした独自の奨学金制度を創設している。中森コラムでは、全国大学生協連が毎年実施している「学生生活実態調査」の最新結果から見えてきた問題点と大学生のリアルな声を紹介いただいた。
本特集が、日本の高等教育の学費・奨学金問題とその背景について考え、生協が今後この問題にどう関わったらよいのかを議論するきっかけとなれば幸いである。
(柳下 剛)
主な執筆者:大内裕和、本田由紀、矢野眞和、小林雅之、河村小百合、岩重佳治、福島愛由、中森一朗
目次
- ●巻頭言
- ノウフクの日(中嶋康博)
- ●特集 日本の大学の学費・奨学金問題を考える
- 学費・奨学金問題の現在(大内裕和)
- 日本の高学費問題の社会的背景(本田由紀)
- 大学を「会社」から「社会」に戻す(矢野眞和)
- 学生支援制度の問題点と今後の課題(小林雅之)
- 大学の供給過剰問題への対応(河村小百合)
- コラム1 貸与奨学金の問題点──相談・救済の現場から(岩重佳治)
- コラム2 コープさっぽろの奨学金の取り組み(福島愛由)
- コラム3 学費・奨学金問題の『リアル』を考える(中森一朗)
- ●IYC2025の機会に協同組合の価値を再考する(第1回)
- コープあいちの日間賀島への宅配事業(鈴木 岳)
- ●国際協同組合運動史(第37回)
- 1960年第21回ローザンヌICA大会①(鈴木 岳)
- ●本誌特集を読んで(2025・2)
- (髙須啓太)
- ●新刊紹介
- 杉本貴志・北川太一監修『図解知識ゼロからの協同組合入門』(鈴木 岳)
- ●研究所日誌
- ●公開研究会「日本の大学の学費と奨学金問題を考える」(4/22)
- ●アジア生協協力基金2025年度助成先決定のお知らせ
- ●生協総研賞・第21回助成事業研究論文集
- ●『生協総研レポート』No.102『生協共済研究会2019年度~ 2024年度の歩み』
- ●『生協総研レポート』No.103『生協による市民活動支援の現状と課題