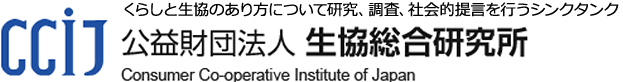- ホーム
- 刊行物
- 生活協同組合研究バックナンバー一覧
- 2023年度
刊行物
生活協同組合研究バックナンバー一覧
2023年度
(各論考のタイトルをクリックするとJ-STAGEに公開されている当該論考のPDFをご覧になれます)
2024年3月号(Vol.578)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 先祖代々の墓が消える!? | 岩田三代 |
| ■特集 健康寿命の延伸のために | |
| 地域で取り組むフレイル予防──健康長寿と幸福長寿の実現に向けて── | 飯島勝矢 |
| ビッグデータを活用した新しい健康増進活動 | 中路重之・村下公一・三上達也 |
| 筋活で延ばす健康寿命 | 町田修一 |
| 食物繊維の健康寿命への効用 | 青江誠一郎 |
| 食生活からの認知症予防 | 大塚 礼 |
| 食生活によるフレイル対策 | 本川佳子 |
| 「CO・OP共済 健康づくり支援企画」から考える生協の「健康づくり」の取り組みについて | 田中美樹 |
| ■研究と調査 | |
| 芸術従事者の協同組合モデル──現代美術における芸術従事者の活動環境に資する連帯── | 木原 進 |
| ■国際協同組合運動史(第24回) | |
| 戦時下における国際協同組合同盟(ICA)① | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2024・1) | |
| 1月号特集 世界的な食料危機の中で,持続可能で健康的な食のあり方と生協の役割を考える | 大木 茂 |
| 1月号特集 世界的な食料危機の中で,持続可能で健康的な食のあり方と生協の役割を考える | 北川太一 |
| ■新刊紹介 | |
| 野口敬夫・曹斌編著『農業協同組合の組織・事業とその展開方向 ─多様化する農業経営への対応』 | 三浦一浩 |
| ■研究所日誌 | |
2024年2月号(Vol.577)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 自由からの逃走 | 神野直彦 |
| ■特集 消費者への情報提供とコミュニケーションの在り方を考える | |
| 広告コミュニケーションを取り巻く現状と期待される機能 | 田部渓哉 |
| “コミュニケーション”から改善する顧客体験(CX)──「消費者と企業のコミュニケーション実態調査 2023-2024」徹底解説── | 小林聖和 |
| サーキュラーエコノミーと消費者コミュニケーション | 西尾チヅル・高山美和 |
| ゲノム編集食品のリスクコミュニケーション | 小泉 望 |
| 生協のイメージ形成と消費者との接点の関係──2022年度デジタルコミュニケーションタスクフォース若年層調査の結果から── | 宮﨑達郎 |
| ■研究と調査 | |
| 大学生協学生委員会における学びと成長の学習構造 | 難波博史 |
| ■国際協同組合運動史(第23回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1937年第15回パリ大会② | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・12) | |
| 12月号特集 新型コロナ禍以後の葬祭事情と生協 | 本間紀子 |
| 12月号特集 新型コロナ禍以後の葬祭事情と生協 | 小塚和行 |
| ■研究所日誌 | |
2024年1月号(Vol.576)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 第10次中計初年度の生協総合研究所のデジタル化の取り組みについて | 藤田親継 |
| ■特集 世界的な食料危機の中で、持続可能で健康的な食のあり方と生協の役割を考える | |
| 開会挨拶・解題 | 中嶋康博 |
| 私たちの食生活と人・地球の健康 | 飯山みゆき |
| 食料・農業・農村基本法の見直しに向けて | 杉中 淳 |
| 未来に向けた「食」と「農」──これからの課題と可能性── | 下川 哲 |
| パネルディスカッション「持続可能で健康的な食のあり方と生協の役割」 | 飯山みゆき・杉中 淳・下川 哲・河野康子・藤田親継(進行役) |
| 閉会の挨拶 | 藤田親継 |
| ■国際協同組合運動史(第22回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1937年第15回パリ大会 | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・11) | |
| 11月号特集 100年前の生協:消費組合運動の広がりと関東大震災 | 和田武広 |
| 11月号特集 100年前の生協:消費組合運動の広がりと関東大震災 | 青竹 豊 |
| ■研究所日誌 | |
2023年12月号(Vol.575)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| リスペクトと崖っぷちの相互扶助 | 米山高生 |
| ■特集 新型コロナ禍以後の葬祭事情と生協 | |
| 葬儀をめぐる変化と動向の諸相 | 田中大介 |
| 昨今の国内外の火葬事情 | 武田 至 |
| いわて生活協同組合の葬祭事業──セリオの展開── | 藤原高宏〈聞き手:鈴木 岳〉 |
| 葬送とお墓のゆくえ | 小谷みどり |
| 兵庫県高齢者生活協同組合の実践──終活と共同墓を中心に── | 藤山 孝〈聞き手:鈴木 岳〉 |
| ■研究と調査 | |
| コープ共済のライフプランニング活動の原点──1990年代の保障の見直しムーブメント── | 渡部博文 |
| ■国際協同組合運動史(第21回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1934年第14回ロンドン大会 | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・10) | |
| 10月号特集 子育て支援の現状と今後の展望 | 久保ゆりえ |
| 10月号特集 子育て支援の現状と今後の展望 | 志波早苗 |
| ■研究所日誌 | |
| ■兵藤釗先生を偲んで | 武田晴人 |
2023年11月号(Vol.574)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| くらしの願いに寄り添い,「ともに」の力で未来へ | 熊﨑 伸 |
| ■特集 100年前の生協:消費組合運動の広がりと関東大震災 | |
| 賀川豊彦の3つの時代と関東大震災 | 伊丹謙太郎 |
| 大正デモクラシーと新興消費組合の時代 | 斎藤嘉璋 |
| 消費組合共働社と平沢計七──亀戸事件100年からの検証── | 大和田茂 |
| 戦前最大の生協,家庭購買組合 | 小嶋 翔 |
| 関東大震災とボランティア──他団体と消費組合の活動を比較して── | 尾崎智子 |
| ■国際協同組合運動史(第20回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1934年第14回ロンドン大会開催までの経緯とドイツ問題 | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・9) | |
| 9月号特集 誰もが自由に,安心して外出できる社会を創る | 髙橋 健 |
| 9月号特集 誰もが自由に,安心して外出できる社会を創る | 高木英孝 |
| ■研究所日誌 | |
2023年10月号(Vol.573)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 子どもや若者の居場所 | 天野恵美子 |
| ■特集 子育て支援の現状と今後の展望─子育て家庭の「孤立」をどう防ぐのか─ | |
| 子育てをめぐる孤立と孤独 | 宮本みち子 |
| 深刻化する子育ての孤立と解決のカギ──少子化対策を超えて,全ての親と子を支える「共同養育」の社会へ── | 榊原智子 |
| 子育て支援におけるIT機器・SNS利用の意義と可能性 | 石井クンツ昌子 |
| 地域づくりとしての育児の「協同」──ケアリング・デモクラシーをめぐる世田谷の実践── | 相馬直子・松田妙子 |
| 「生活の協同」としての保育──戦後初期における東京自由保育園の事例から── | 三浦一浩 |
| ■国際協同組合運動史(第19回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1930年第13回ウィーン大会② | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・8) | |
| 8月号特集 今改めて原子力発電について考える | 小野 一 |
| ■研究所日誌 | |
2023年9月号(Vol.572)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 産地交流の大切さを想う | 大信政一 |
| ■特集 誰もが自由に,安心して外出できる社会を創る | |
| 障害の「社会モデル」から「外出の自由」を考える | 石川 准 |
| 高齢期における外出と心身の健康──閉じこもり高齢者に対する調査結果から── | 山崎幸子 |
| バリアフリー社会の実現を目指して──交通アクセス運動と東京オリパラを契機としたさらなるバリアフリーの推進── | 佐藤 聡 |
| 子どもが安心して遊べる道路は大人にも楽しい交流の場──日本へのボンエルフ導入を考える── | 薬袋奈美子 |
| 外出を後押しし,地域住民の交流を促進するはるな生協の「えんがお」 | 佐藤紀代子〈聞き手:山崎由希子〉 |
| コラム 多様な世代が外出しやすくなる社会環境の構築について | 大森宣暁 |
| ■国際協同組合運動史(第18回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1930年第13回ウィーン大会① | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・7) | |
| 7月号特集 防災・減災に向けて 今からできること,すべきことを考える | 岡田卓巳 |
| 7月号特集 防災・減災に向けて 今からできること,すべきことを考える | 根本篤司 |
| ■新刊紹介 | |
| 斉藤弥生・V.ペストフ(編)『コ・プロダクションの理論と実践参加型福祉・医療の可能性』 | 藤田親継 |
| ■研究所日誌 | |
2023年8月号(Vol.571)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 生協とSDGs | 小栗崇資 |
| ■特集 今改めて原子力発電について考える | |
| 原子力政策の再検証:その合理性,正当性を問う | 鈴木達治郎 |
| 再エネ主力電源化へ,踏むべきはブレーキではなくアクセル | 飯田哲也 |
| 原発再稼働で電力需給ひっ迫は解決するのか? | 青柳聡史 |
| 戦時下の原発リスク──ロシアのザポリージャ原発占拠が明らかにした原発の弱さと危険── | 竹内敬二 |
| ALPS処理水に関する住民意識──2019年,2021年,2023年調査より── | 関谷直也 |
| 「アルプス(ALPS)処理水海洋放出に反対する署名」の取り組みについて | 河野雪子 |
| ■国際協同組合運動史(第17回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1927年第12回ストックホルム大会② | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・6) | |
| 6月号特集 世界の協同組合によるエネルギー事業と日本 | 河原林 孝由基 |
| 6月号特集 世界の協同組合によるエネルギー事業と日本 | 豊田 陽介 |
| ■研究所日誌 | |
2023年7月号(Vol.570)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「関東大震災から100年」防災・減災の意識と「備え」への取り組みを社会全体で日常の生活に定着させたい | 稲村浩史 |
| ■特集 防災・減災に向けて 今からできること,すべきことを考える | |
| 地震災害に備えるための防災教育 | 平田 直 |
| これからの巨大災害にどう備えるか? 個々人のイマジネーションを! | 西川 智 |
| 災害から命を守る「タイムライン防災」と「コミュニティ防災会議」を拡げよう | 松尾一郎 |
| 人が集まり地域のつながりを生む防災訓練─イザ!カエルキャラバン!─ | 石田有香 |
| 生協における防災・減災の取り組み事例 | 前田昌宏・蔦 直宏 |
| こくみん共済coopにおける防災・減災の取り組みについて | こくみん共済coop |
| 在宅避難を想定したホームサバイバルトライアルの勧め─各自の家庭に電気・水道・ガスを遮断した状態を作り出し「疑似被災体験」に挑戦する─ | 玉田太郎 |
| 新しい防災教育「被災したあなたを助けるお金とくらしの話」のすすめ | 岡本 正 |
| ■国際協同組合運動史(第16回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1927年第12回ストックホルム大会① | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・5) | |
| 5月号特集 ワーカーズ・コレクティブの現在地 | 高橋弘幸 |
| 5月号特集 ワーカーズ・コレクティブの現在地 | 香西 幸 |
| ■研究所日誌 | |
2023年6月号(Vol.569)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 必需財であるエネルギーへの取り組みは生協運動そのもの「コンセントの向こう側」の社会課題を組合員とともに考え行動する | 岩山利久 |
| ■特集 世界の協同組合によるエネルギー事業と日本 | |
| アルゼンチンの電力協同組合 | 石塚秀雄 |
| ドイツにおける市民エネルギー協同組合の動向 | 寺林暁良 |
| イタリアにおけるエネルギー協同組合の動向──legacoop第41回大会(2023年3月)で発刊された資料「レガコープ~エネルギーコミュニティ」の概要紹介を中心に── | 田中夏子 |
| アメリカにおける電力協同組合の展開 | 三浦一浩 |
| 再生可能エネルギーの担い手としての農業協同組合の現状と課題──中国地方の小水力発電所を事例に── | 本田恭子 |
| コラム 協同組合とエネルギー供給 | 三浦一浩 |
| 国際協同組合運動史(第15回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)1924年第11回ヘント大会 | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・4) | |
| 4月号特集 高齢者の生活と消費 | 安部裕子 |
| 4月号特集 高齢者の生活と消費 | 小林由比 |
| ■新刊紹介 | |
| 小栗崇資『社会・企業の変革とSDGs─マルクスの視点から考える─』 | 藤田親継 |
| ■私の愛蔵書 | |
| 室田 武『電力自由化の経済学』 | 三浦一浩 |
| ■研究所日誌 | |
2023年5月号(Vol.568)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| コロナ禍のCSW67とジェンダーNGOs | 吉村真子 |
| ■特集 ワーカーズ・コレクティブの現在地 | |
| ワーカーズ・コレクティブの歩みとこれから | 伊藤由理子 |
| 対談:ワーカーズ・コレクティブの現在 | 木村満里子・井上浩子〈聞き手:三浦一浩〉 |
| 労働者協同組合法時代におけるワーカーズ・コレクティブと社会的連帯経済─神奈川における新しい中間支援組織作りの模索から─ | 藤井敦史 |
| 変遷期におけるワーカーズ・コレクティブの新しい展開─更新する運動性を神奈川・東京の実態調査から探る─ | 菰田レエ也 |
| これからのワーカーズ・コレクティブの課題─「雇用されないもう一つの働き方」だけでなく「ディーセント・ワーク」の実現をめざして─ | 白井和宏 |
| NPO法から見た労働者協同組合法 | 関口宏聡 |
| コラム 多様な事業展開はワーカーズ・コレクティブの醍醐味 | 中野寿ゞ子 |
| ■国際協同組合運動史(第14回) | |
| 1921年第10回バーゼル大会②とその後の動向 | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・3) | |
| 3月号特集 消費者団体訴訟制度の充実・強化を求めて | 中村年春 |
| 3月号特集 消費者団体訴訟制度の充実・強化を求めて | 西島秀向 |
| ■研究所日誌 | |
2023年4月号(Vol.567)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| わが国の食料安全保障をめぐって | 中嶋康博 |
| ■特集 高齢者の生活と消費 | |
| 高齢者の消費の現状 | 坊美生子 |
| 高齢期における外出時の移動手段:健康の視点から | 阿部 巧 |
| 高齢者就労の特徴と課題:企業,労働者双方の視点から | 森山智彦 |
| 地域コミュニティにおけるつながりづくりとICTの活用の可能性 | 菅原育子 |
| 全国生協組合員意識調査からみる高齢層の生協利用の変化 | 宮﨑達郎 |
| ■国際協同組合運動史(第13回) | |
| 国際協同組合同盟(ICA)第10回バーゼル大会 | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2023・2) | |
| 2月号特集 職場におけるダイバーシティ推進 | 岩田三代 |
| 2月号特集 職場におけるダイバーシティ推進 | 荒井絵理菜 |
| ■研究所日誌 | |