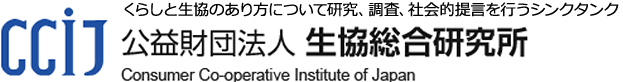- ホーム
- 刊行物
- 生活協同組合研究バックナンバー一覧
- 2019年度
刊行物
生活協同組合研究バックナンバー一覧
2019年度
(各論考のタイトルをクリックするとJ-STAGEに公開されている当該論考のPDFをご覧になれます)
2020年3月号(Vol.530)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 健康寿命の男女差と食生活 | 樋口恵子 |
| ■特集 食の簡便化志向の現在 | |
| 調理食品に関わる消費の動向について | 宮﨑達郎 |
| ミールキット市場 拡大を続ける3つの要因 | 阿古真理 |
| 業界50年のヒット商品から未来を探る──「手間抜き」が心に響く家庭の食事情── | 山本純子 |
| 食品添加物の安全性は今どうなっているのか | 長村洋一 |
| 諸国における食の簡便化事情 | 鈴木 岳 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情⑫<最終回> | |
| レジ袋有料義務化の概要と課題、他社の動き | 小野光司 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より⑫ | |
| 『社会運動』 | 香西 幸 |
| ■海外情報 | |
| 第7回ヨーロッパ社会的企業研究ネットワーク(EMES) 国際学会参加報告 | 山崎由希子 |
| ■本誌特集を読んで(2020・1) | |
| 1月号特集 生協職員が活き活きと働き続け,定着できる職場づくりのために | 秃 あや美 |
| 1月号特集 生協職員が活き活きと働き続け,定着できる職場づくりのために | 北村 洋 |
| ■新刊紹介 | |
| 樋口恵子著『老~い、どん!』 | 山崎由希子 |
| ■研究所日誌 | |
2020年2月号(Vol.529)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「生」を「共」にする | 神野直彦 |
| ■特集 保育・教育の無償化と子育て支援の変化 | |
| 幼児教育・保育無償化のとらえ方と抜本的改善の方向性 | 中山 徹 |
| 子育ての社会化と支援の進行:家族主義と福祉レジーム転換 | 相馬直子 |
| 専業主婦のいない?スウェーデンの就学前教育と協同組合 | 小田巻友子 |
| 子育て支援の大きな領域としての保育 ─日本の消費生活協同組合が保育事業に踏み出せないのはなぜか─ | 近本聡子 |
| コープおおいたの子育て支援事業 ~認可保育園と学童クラブの運営~ | 渡部博文 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情⑪ | |
| スマホではなく、生活を変える5G | 吉田健太郎 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より⑪ | |
| 『いのちとくらし研究所報』 | 石澤香哉子 |
| ■継承・発信 平和の取り組み⑤ | |
| 被爆体験証言集『つたえてください あしたへ……』 第25集の発刊にあたり | 後藤誠治・原田健二郎 |
| ■残しておきたい協同のことば(追補版3) | |
| ホセ・マリア・アリスメンディアリエタ | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2019・12) | |
| 12月号特集 消費者庁・消費者委員会創設から10年 | 元山鉄朗 |
| 12月号特集 消費者庁・消費者委員会創設から10年 | 丸山千賀子 |
| ■研究所日誌 | |
2020年1月号(Vol.528)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 共助としての生協の役割 | 中嶋康博 |
| ■特集 生協職員が活き活きと働き続け、定着できる職場づくりのために―生協の未来を担う人材の確保と育成― | |
| 開会の挨拶 | 中嶋康博 |
| 多様化する職員とダイバーシティ経営 | 平田未緒 |
| 多様な働き方ができる人財活用の取り組み | 中川敦士 |
| パート女性社員の活用 | 梅崎 修 |
| 多様な職員を活かす働き方と組織の在り方を考える | 島崎安史 |
| パネルディスカッション① 討議 | |
| 職場マネジメントの現状と課題 | 佐藤博樹 |
| 「組織の理念共有・共感」への取り組みと「働き方改革」の取り組み | 石井 亮 |
| 経営理念の浸透と上司のリーダーシップが職員の就業継続意思に与える効果 | 島貫智行 |
| 理念共有や社会活動は職員の定着を促すか | 小野晶子 |
| 全国の生協の未来を担う人材の確保・定着・育成に向けた取り組みの全体動向と日本生協連全国生協・人づくり支援センターについて | 近藤麻子 |
| コープあいちの職場マネジメントの取り組みと課題について | 川端宏一 |
| パネルディスカッション② 討議 | |
| 閉会の挨拶 | 和田寿昭 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情⑩ | |
| 協同組合の可能性を広げること~「プラットフォーム協同組合」について~ | 中野 理 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より⑩ | |
| 『協同の発見』 | 久保ゆりえ |
| ■本誌特集を読んで(2019・11) | |
| 11月号特集 生協の共済を取り巻く事業環境 | 鈴木 穣 |
| 11月号特集 生協の共済を取り巻く事業環境 | 梶浦孝弘 |
| 生協総研賞 第12回表彰事業・講評 | |
| ■研究所日誌 | |
2019年12月号(Vol.527)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 市民社会と政府 | 中島智人 |
| ■特集 消費者庁・消費者委員会創設から10年 | |
| 消費者庁と「消費者市民社会」の形成──消費者庁創設10周年に寄せて── | 阿南 久 |
| 消費者法と消費者政策──この10年を振り返って── | 河上正二 |
| デジタル社会における消費者政策の課題──時代の変化に対応した政策立案をめざして── | 千葉惠美子 |
| 消費者裁判手続特例法制定に至る運動と現在の到達点。今後への期待 | 磯辺浩一 |
| 消費者庁10年の行政評価 | 拝師徳彦 |
| 意見交換会「消費者庁・消費者委員会に期待を込めて物申す」 | |
| コラム1 デジタル革命の中心に消費者を──第21回国際消費者機構世界大会の参加報告── | 鶴田 健 |
| コラム2 G20消費者政策国際会合(9/5~6 於・徳島)傍聴報告 | 有田芳子 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情⑨ | |
| SDGs達成のための財源として注目される「国際連帯税」 | 柳下 剛 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より⑨ | |
| 『地域と協同』 | 鈴木 岳 |
| ■継承・発信 平和の取り組み④ | |
| 次の世代に被ばく・戦争体験を継承する | 野村泰史 |
| ■本誌特集を読んで(2019・10) | |
| 10月号特集 乳製品をめぐる最新事情 | 大木 茂 |
| 10月号特集 乳製品をめぐる最新事情 | 川口啓明 |
| ■研究所日誌 | |
2019年11月号(Vol.526)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| プラットフォーマーと協同組合 | 小栗崇資 |
| ■特集 生協の共済を取り巻く事業環境 | |
| 人生100年時代のライフプランと共済 | 藤川 太 |
| 新しい保険業態「少額短期保険」発展の原動力とは ~経営面・商品開発面の特色~ | 小泉武彦 |
| 米国生保市場の状況 | 松岡博司 |
| 生命保険における健全性規制の動向と保険会社の対応状況 | 植村信保 |
| 協同組合共済をめぐる環境変化と対応 | 武田俊裕 |
| コラム1 パルシステム共済連『たすけあい活動委員会』の取り組み | 渡辺恵輔 |
| コラム2 私たちの使命と想い ~新ブランド「こくみん共済 coop」の策定~ | 酒井 健 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情⑧ | |
| 消費税増税直前の消費者意識 | 中村良光 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より⑧ | |
| 『参加システム』 | 三浦一浩 |
| ■海外情報 | |
| フランスにおける新たな協同組合運動 ─各地で設立される「労働参加型生協」の店舗─ | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2018・9) | |
| 9月号特集 大丈夫か? 大学生の食生活a> | 奈良由美子 |
| 9月号特集 大丈夫か? 大学生の食生活 | 山田香織 |
| ■新刊紹介 | |
| 和田武広著『共済事業の源流をたずねて 賀川豊彦と協同組合保険』 | 中林真理子 |
| ■研究所日誌 | |
2019年10月号(Vol.525)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 大学生協連発足60周年 | 古田元夫 |
| ■特集 乳製品をめぐる最新事情 | |
| 日本における乳製品の生産と供給の課題 | 小林信一 |
| 牛乳・乳製品の国内消費の変化と最近の国際市場の動向 | 小田志保 |
| 牛乳・乳製品と健康 | 上西一弘 |
| 子どもと大人の牛乳アレルギーと対応について | 伊藤節子 |
| 生協と牛乳のかかわりの変遷と現在 | 鈴木 岳 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情⑦ | |
| NPT再検討会議と核兵器廃絶をめぐる最新動向 | 堀内聡子 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より⑦ | |
| 『信金中金月報』 | 久保ゆりえ |
| ■継承・発信 平和の取り組み③ | |
| 千葉県生協連70周年記念事業「子どもたちに平和な未来を2019」を開催しました | 小田川和恵 |
| ■研究と調査 | |
| 大学生の自然災害に対する危機認識と対応行動の現状 | 水木千春・朴恵淑 |
| ■本誌特集を読んで(2019・8) | |
| 8月号特集 「シェアリングエコノミー」を学ぶ | 白井和宏 |
| 8月号特集 「シェアリングエコノミー」を学ぶ | 毎田伸一 |
| ■研究所日誌 | |
2019年9月号(Vol.524)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 大学生の食生活の現状と大学生協の役割 | 白石正彦 |
| ■特集 大丈夫か? 大学生の食生活 ―大学での食育と大学生協の食堂事業の役割 | |
| 学生期の健康と食事 | 杉田義郎 |
| 大学生の健康実態と食生活指導 | 山本眞由美 |
| 大学生の食習慣はどのように形成されるか ―家庭、学童期の食習慣と大学生の食育の重要性 | 江坂美佐子 |
| 女子大学生の健康意識と食生活、食に関する情報行動 | 石見百江 |
| 健康な生活は朝ごはんから ―大東文化大学の「朝ごはんプロジェクト」と食育講義 | 蕪木智子 |
| コラム1 大学生の食生活が心配 ―学生の生活リスク講座プロジェクトが目指すもの― | 高森裕子 |
| コラム2 大学生の食の自立に向けた提案活動 ―大学生協の学食情報サイト「学生どっとコープ」― | 高橋亮子 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情⑥ | |
| LGBT・SOGIはいま | 下平 武 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より⑥ | |
| 『まちと暮らし研究』の概要と沿革 | 石澤香哉子 |
| ■継承・発信 平和の取り組み② | |
| 生活協同組合コープかごしま「6.17平和のつどい」 | 北 康孝 |
| ■本誌特集を読んで(2019・7) | |
| 7月号特集 外国人とのよりよい共生のために | 神田すみれ |
| 7月号特集 外国人とのよりよい共生のために | 向井忍/堀家春野 |
| ■研究所日誌 | |
2019年8月号(Vol.523)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 社会的養護のもとで育った子どもたちの独り立ちを応援する | 宮本みち子 |
| ■特集 「シェアリングエコノミー」を学ぶ | |
| 概説 日本におけるシェアリングエコノミーの現在 | 市川拓也 |
| ヨーロッパにおけるシェアリングエコノミーをめぐる議論と近年の状況 | 穂鷹知美 |
| 新法施行から1年余り、日本の民泊はどこへ行く | 高田 泰 |
| シェアリングエコノミーに懸念される労働問題 | 山崎 憲 |
| 韓国・ソウル市におけるシェアリング・サービスの進展 | 鄭 城尤 |
| コラム シェアリングエコノミーの国内事例の現況 | 鈴木 岳 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情⑤ | |
| 問われる大学医学部入試における女性等への差別 ―消費者団体訴訟の取組― | 磯辺浩一 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より⑤ | |
| 『農中総研 調査と情報』(『農中総研情報』) | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2019・6) | |
| 6月号特集 日本農業の現在地を把握する | 勝又博三 |
| 6月号特集 日本農業の現在地を把握する | 樫原弘志 |
| ■理事長交代あいさつ | |
| ■研究所日誌 | |
2019年7月号(Vol.522)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 成年年齢の引き下げと家庭科 | 天野晴子 |
| ■特集 外国人とのよりよい共生のために | |
| 国境を越える人の移動と移民政策 ─その影響と課題を考える─ | 明石純一 |
| 入管法改正と日本の在留資格,永住権について | 浅川晃広 |
| 技能実習制度へのニーズの所在とその隘路 ─「2つの二重構造」との関連を手がかりに | 山口 塁 |
| 政府が目指す「共生社会」とは何か ─その課題と展望─ | 石原 進 |
| 生協における外国人雇用の現状と課題 | 高多 洋 |
| コラム 日本人の移民小史とブラジル・コチア農業協同組合の追憶 | 鈴木 岳 |
| ■継承・発信 平和の取り組み① | |
| 未来につなぐ被爆の記憶体験会 | 中村良光 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情④ | |
| 電力自由化と生協の電気小売の最新事情 ─現在の課題とこれから大切にしていきたい視点 | 高橋怜一 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より④ | |
| 『共済総研レポート』 | 久保ゆりえ |
| ■本誌特集を読んで(2019・5) | |
| 5月号特集 人口減少社会下の生協組合員のくらし | 齋藤雅通 |
| 5月号特集 人口減少社会下の生協組合員のくらし | 青木雅生 |
| 5月号特集 人口減少社会下の生協組合員のくらし | 及川昭夫 |
| ■研究所日誌 | |
2019年6月号(Vol.521)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「競争」と「協同」 ─独占禁止法における協同組合の立ち位置─ | 山部俊文 |
| ■特集 日本農業の現在地を把握する | |
| 近年の競争力強化を目的とした農業政策について | 植田展大 |
| 農産物に関わる貿易自由化の動向とその影響 | 齋藤勝宏 |
| AI・ロボットが変える日本農業の未来 | 窪田新之助 |
| 日本人の農産物の国産志向はどこまで続くか | 川口啓明 |
| 生協産直の交流・コミュニケーションを改めて考える ─第10回全国生協産直調査の結果より─ | 宮﨑達郎 |
| ■海外情報 | |
| カナダ・ノーウェスト医療生協調査報告 | 山崎由希子 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情③ | |
| 食品○○で健康になれるか? 「日本人の食事摂取基準」で考える | 児林聡美 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より③ | |
| 『農林金融』 | 三浦一浩 |
| ■本誌特集を読んで(2019・4) | |
| 4月号特集 生協の生活相談・貸付事業の広がり | 前田裕保 |
| 4月号特集 生協の生活相談・貸付事業の広がり | 新里宏二 |
| ■新刊紹介 | |
| 早瀬 昇『「参加の力」が創る共生社会』 | 中村良光 |
| ■私の愛蔵書 | |
| 都築忠七『エリノア・マルクス 1855-1898』 | 鈴木 岳 |
| ■研究所日誌 | |
2019年5月号(Vol.520)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 2018年度全国生協組合員意識調査に思うこと | 加藤好一 |
| ■特集 人口減少社会下の生協組合員のくらし ―2018年度全国生協組合員意識調査をベースに― | |
| 人口減少社会への向き合い方 | 作野広和 |
| 組合員の今を知り、生協の未来を考える | 炭谷 昇 |
| 生協は現代の「ワンオペ育児」「ワンオペ生活」を支えているのか ──専業主婦がマイノリティとなった現代の生活変動── |
近本聡子 |
| 対応が迫られる生協組合員の高齢化と低利用化 | 宮﨑達郎 |
| 2018年度 鳥取県生協組合員意識調査の結果と今後の課題について | 小林茂樹 |
| 調査回答に回答者の利用・登録データを紐づけての分析 | 三原章次 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情② | |
| ゲノム編集技術を利用した食品とは ~いま、何が問われているのか | 森田満樹 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より② | |
| 『季刊 くらしと協同』 | 久保ゆりえ |
| ■本誌特集を読んで(2019・3) | |
| 3月号特集 次の生協リーダーに知ってほしい『震災』の本当の話 | 戸田真理 |
| 3月号特集 次の生協リーダーに知ってほしい『震災』の本当の話 | 脇田泰子 |
| ■新刊紹介 | |
| ヘンリー・ハンズマン著、米山高生訳『企業所有論─組織の所有アプローチ』 | 栗本 昭 |
| ■研究所日誌 | |
2019年4月号(Vol.519)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 決まりごとが通用しない | 生源寺眞一 |
| ■特集 生協の生活相談・貸付事業の広がり | |
| 家計の経済的困窮と社会的孤立の解消 ──包摂する地域社会に向けて── | 重川純子 |
| なぜ生協が生活相談・貸付事業に取り組むのか ──低所得者・生活困窮者等の金融福祉の観点から── | 角崎洋平 |
| これからの家計改善支援事業を展望する | 佐藤順子 |
| 生協の生活相談・貸付事業を取り巻く事業環境と事業課題 | 上田 正 |
| 生活相談・貸付事業から見えたくらしと家計の課題と生協の役割 | 渡邉 淳 |
| 生活クラブ生協(千葉)の生活相談・家計再生支援貸付事業 | 依知川 稔 |
| 労働金庫の多重債務問題等の取り組み | 塩原洋光 |
| ■連載 フォーカス くらしと社会の最新事情① | |
| 教育費をめぐる最新動向 ~日本生協連「家計・くらしの調査」から | 大部桂一 |
| ■連載 協同組合系研究所の逐次刊行物より① | |
| 『協同組合研究誌 にじ』 | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで(2019・2) | |
| 2月号特集 葬儀の変容とライフエンディング─お葬式の意味を考える | 小野修三 |
| 2月号特集 葬儀の変容とライフエンディング─お葬式の意味を考える | 中久保邦夫 |
| ■研究所日誌 | |