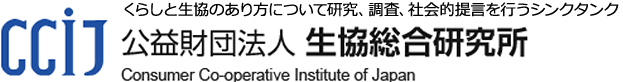- ホーム
- 刊行物
- 生活協同組合研究バックナンバー一覧
- 2012年度
刊行物
生活協同組合研究バックナンバー一覧
2012年度
(各論考のタイトルをクリックするとJ-STAGEに公開されている当該論考のPDFをご覧になれます)
2013年3月号(Vol.446)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「買い物」という生の快楽 組合員の生きる喜びを支える生協 | 樋口恵子 |
| ■特集 全国生協組合員意識調査から見えること | |
| 生協をとりまく経済環境とニーズに対応できる柔構造組織づくり | 若林靖永 |
| 2012年度全国生協組合員意識調査調査概要について | 三谷和央 |
| 格差社会の中の北海道購買動向──コープさっぽろマーケティング室の取り組み── | 米田敬太朗 |
| 2012年度全国組合員意識調査から | 千葉 徹 |
| 第5回公開研究会(福岡会場)でのディスカッションノート | (編集)近本聡子 |
| 過去の延長線上にない新たな時代の家計運営 | 内藤眞弓 |
| 生計と節約のあり方を提案する一般書のアンソロジー | 鈴木 岳 |
| コラム イタリア生協連(ANCC),年次経済分析報告書の修正版を発行「消費と流通 2012年度版」 | 大津荘一 |
| ■支援活動から見えてきたもの⑦ | |
| フードバンクによる被災地支援の現状と課題 | 髙橋陽佑 |
| ■残しておきたい協同のことば 第24回 | |
| ファン・B・フスト | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2013年1月号「東日本大震災2年目の支援課題」 | 喜多 裕彦 |
| 2013年1月号「東日本大震災2年目の支援課題」 | 石原 慎士, 李 東勲 |
| ■新刊紹介 | |
| 野原一仁 著『近代協同組合成立の研究日本における「ロッチディル」共立商社運動の軌跡』 | 井内智子 |
| ■研究所日誌 | |
2013年2月号(Vol.445)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「デフレ脱却」策の先に見える風景 | 武田晴人 |
| ■特集 水─国際水協力年を記念して | |
| 世界の水と日本──国連ミレニアム目標と国際水協力年── | 沖 大幹 |
| 日本の水道の「過剰」「過疎」問題と水ガバナンス | 保屋野初子 |
| 小水力発電の可能性と普及に向けた課題 | 小林 久 |
| 琵琶湖の水環境をめぐる市民運動史──石けん運動から流域環境保全まで── | 井手慎司・伊藤真紀 |
| 四国三郎吉野川水系の上下流問題 | 林 薫平 |
| コラム1 安全な水と美味しい水──バングラデシュの井戸水── | 斉藤 進 |
| コラム2 日本の一般世帯における水道料金のしくみと地域格差 | 鈴木 岳 |
| コラム3 イタリア生協連「水道水の利用促進キャンペーン」 | 大津荘一 |
| ■コラム 4 | |
| フランス史から眺める水事情・水戦略 | 鈴木 岳 |
| ■支援活動から見えてきたもの⑥ | |
| パルシステム東京の震災復興支援 | 井内智子 |
| ■海外レポート | |
| 国際協同組合サミット研究者セミナー参加レポート | 山崎由希子 |
| ■研究レポート | |
| 国際公共経済学会・京都大会 | 栗本 昭 |
| ■残しておきたい協同のことば 第23回 | |
| エドガー・ミヨー | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年12月号「国際協同組合年を超えて:成果と課題」 | 堀江 智子 |
| 2012年12月号「国際協同組合年を超えて:成果と課題」 | 米倉 克良 |
| ■新刊紹介 | |
| ジョセフ・E.スティグリッツ著『世界の99%を貧困にする経済』 | 栗本 昭 |
| ■研究所日誌 | |
2013年1月号(Vol.444)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 国際協同組合同盟(ICA)臨時総会,第10回ICAアジア太平洋地域(AP)総会に参加して | 芳賀唯史 |
| ■特集 東日本大震災2年目の支援課題 | |
| 開会挨拶 | 生源寺眞一 |
| 震災復興水産業の再建と市民参加の視点 | 高成田 享 |
| 三陸地域再建に向けた地域商業と地域ブランド形成の課題 | 加藤 司 |
| 高成田・加藤報告に対するコメント | 杉本貴志 |
| 原子力被災地ふくしま復興の課題──ウクライナ,ベラルーシの経験から── | 清水修二 |
| いわて生協からの報告 | 金子成子 |
| みやぎ生協からの報告 | 小澤義春 |
| 福島県生協連からの報告 | 佐藤一夫 |
| パネル・ディスカッション 座長問題提起 | 関 英昭 |
| パネル・ディスカッション 大震災2年目,生活の復興へ | |
| ■支援活動から見えてきたもの⑤ | |
| 地域の暮らしと仕事を再建していくための課題──釜石市鵜住居地区の町内会の聴き取りを通じて── | 田中夏子 |
| ■海外レポート | |
| 国際協同組合サミット公式プレ・イベントImagine 2012参加レポート | 山崎由希子 |
| ■残しておきたい協同のことば 第22回 | |
| ウィリアム・P・ワトキンズ | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年11月号 特集「男女平等参画とくらし・生協」 | 武田 宏子 |
| ■研究所日誌 | |
2012年12月号(Vol.443)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 地域社会づくりと生活協同組合の新たな可能性 | 金子隆之 |
| ■特集 国際協同組合年を超えて:成果と課題 | |
| 対談 国際協同組合年を超えて──達成したことと,これからの課題── | 生源寺眞一・栗本 昭・金子隆之 |
| 日本におけるサードセクターの構築と協同組合 | 後 房雄 |
| 協同組合の柔軟な危機対応力──様々な事例から── | 鍋島由美 |
| 日本の協同組合のIYCの取り組み | 小林真一郎 |
| 世界のIYC(国際協同組合年)活動 | 大津荘一 |
| 「協同組合」は国民にどのように認知されているのか ──『協同組合と生活意識に関するアンケート調査』からみる現代協同組合像── |
大高研道 |
| ■支援活動から見えてきたもの④ | |
| 大学生協ボランティアを通じた学生の学びと成長 | 山崎弘純 |
| ■日本生協の国際協力の歩みVol.7 | |
| 国際交流でエンパワメント──活躍する生協の女性── | 近本聡子 |
| ■残しておきたい協同のことば 第21回 | |
| アレクサンドル・P・クリモフ | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年10月号 特集「水産業復興と協同のネットワーク」 | 江尻 行男 |
| ■新刊紹介 | |
| 中沢卓実・結城康博編著『孤独死を防ぐ』 | 藤井晴夫 |
| ■研究所日誌 | |
2012年11月号(Vol.442)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 国の消費者行政における消費者委員会の位置づけの変化 | 松本恒雄 |
| ■特集 男女平等参画とくらし・生協 | |
| 専業主婦は今後どうなるのか──ジェンダー論と階層論の観点から── | 岩間暁子 |
| マネジメントの改革を進め,職場の男女共同参画の推進を | 佐藤利昭 |
| 生活協同組合をとおした学びと「参加」から「参画」へ──韓国女性民友会生協を事例として── | 朴 賢淑 |
| 食事の世話は母親の仕事? | 蟹江教子 |
| 父親の家事・育児への参画と楽しい食生活 | 吉田大樹 |
| コラム1 「女性力」が日本の将来を支える | 藤井晴夫 |
| コラム2 イタリア・レーガコープのジェンダーの取り組み | 大津荘一 |
| コラム3 震災と宮城の女性 | 井内智子 |
| ■支援活動から見えてきたもの③ | |
| 震災対応状況調査から見えたジェンダー視点に立った支援のあり方 | 建井順子 |
| ■残しておきたい協同のことば 第20回 | |
| ジェームス・P・ワーバス | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年9月号「震災後2年目の福島」 | 清水 文清 |
| 2012年9月号「震災後2年目の福島」 | 北村 俊之 |
| ■新刊紹介 | |
| ジャン=ルイ・ラヴィル著『連帯経済』 | 山崎由希子 |
| ■研究所日誌 | |
2012年10月号(Vol.441)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 市民の事業と市民の政府との好循環 | 庄司興吉 |
| ■特集 水産業復興と協同のネットワーク | |
| JFみやぎ・志津川支所からの報告 | 高橋源一 |
| 石巻商工会議所の取り組みについて | 毛利広幸 |
| 木の屋石巻水産からの報告 | 木村優哉 |
| みやぎ生協「食のみやぎ復興ネットワーク」について | 伊藤光寿 |
| 石巻・気仙沼被災企業の支援 | 石原慎士,李 東勲 |
| ディスカッション「三陸水産業復興に向けて」 | 〈編集:生協総合研究所編集部〉 |
| コラム1 宮城県と石巻の雇用状況 | 鈴木 岳 |
| コラム2 東日本大震災を経てくらしの変化をみる | 近本聡子 |
| コラム3 宮城県(石巻・南三陸)の水産物をめぐって | 鈴木 岳 |
| ■支援活動から見えてきたもの② | |
| パル・パラソルカフェから始まる組合員の支援活動 | 林 美栄子 |
| ■日本生協の国際協力の歩みVol.6 | |
| 生協の協同組合間貿易──賀川豊彦と石黒武重── | 藤井晴夫 |
| ■残しておきたい協同のことば 第19回 | |
| セヴェリン・ヨルゲンセン | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年8月号特集「震災2年目,協同と葛藤」 | 古山 均 |
| 2012年8月号特集「震災2年目,協同と葛藤」 | 青木 博範 |
| ■新刊紹介 | |
| 中川雄一郎・杉本貴志編『協同組合を学ぶ』 | 林 薫平 |
| ■研究所日誌 | |
2012年9月号(Vol.440)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 原発事故から学んだことを忘れてはならない | 蓮見音彦 |
| ■特集 震災後2年目の福島 | |
| 原子力被災地ふくしま復興の課題 | 清水修二 |
| 震災後2年目の飯舘村の状況と,今後の地域再建に向けた課題──飯舘村後方支援の経験と地域計画論からの考察── | 糸長浩司 |
| 原子力災害と協同組合──福島県における協同組合間協同による放射能汚染対策── | 小山良太 |
| 大震災後の福島県内の雇用と生活をめぐって | 鈴木 岳 |
| ■支援活動から見えてきたもの① | |
| 被災地で真の自立を目指す,ソーシャルニットワークプロジェクト | 奥谷京子 |
| ■日本生協の国際協力の歩みVol.5 | |
| 協同組合研究の国際協力と日本の生協 | 栗本 昭 |
| ■残しておきたい協同のことば 第18回 | |
| ヴァイノ・タンネル | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 6月号「続・震災1年―まちとくらしの再建へ」 | 石塚 秀雄 |
| 7月号「社会保障と税をめぐって」 | 矢野 洋子 |
| ■新刊紹介 | |
| ジェフリー・サックス著『世界を救う処方箋:「共感の経済学」が未来を創る』 | 栗本 昭 |
| ■研究所日誌 | |
2012年8月号(Vol.439)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 再び,トインビーに学ぶ | 関 英昭 |
| ■特集 震災2年目,協同と葛藤 | |
| 「棄民から帰民へ」──国家のメルトダウンを許すな── | 山中茂樹 |
| 集団移転というまちづくり──把手共歩へ向けての心得── | 森 傑 |
| 福島県双葉町民を支援するさいたまコープ──子育て層避難者への支援を紹介── | 近本聡子 |
| 東日本大震災における「南米日系の人々の日本に対する想い」と「大熊町の人々の苦悩」に接して | 上田良光 |
| 震災後2年目の福島──「分断」を超えて,協同による復興へ── | 熊谷純一 |
| ■日本生協の国際協力の歩みVol.4 | |
| 医療生協の国際協力の歩み | 東久保浩喜 |
| ■残しておきたい協同のことば 第17回 | |
| ジョルジュ・フォーケ | 鈴木 岳 |
| ■研究所日誌 | |
2012年7月号(Vol.438)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「倫理的銀行」考 | 中川雄一郎 |
| ■特集 社会保障と税をめぐって | |
| 社会保障と税を考える | 神野直彦 |
| 社会保障・税制一体改革に向けて | 駒村康平 |
| 消費税の社会保障目的税化の問題点とは何か | 町田俊彦 |
| 「重税の国」「福祉の国」へ──スウェーデンの高齢者医療・福祉を訪れて── | 樋口恵子 |
| 一体改革の意味と課題──年金制度を中心に── | 田中秀明 |
| 資料 消費税の国際比較 | 編集部 |
| ■日本生協の国際協力の歩みVol.3 | |
| 大学生協の国際協力活動──アジアの大学生協間交流を中心にして── | 栗木敏文 |
| ■残しておきたい協同のことば 第16回 | |
| ゴットリープ・ドゥトワイラー | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年5月号「東日本大震災と生協の共済」 | 相原 才智 |
| ■研究所日誌 | |
2012年6月号(Vol.437)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 災害と男女共同参画統計 | 天野晴子 |
| ■特集 続・震災1年─まちとくらしの再建へ | |
| 地域主体の創造的復興を目指して──社会的共通資本としてのコミュニティの再興── | 風見正三 |
| 震災からの復興と地域ブランド | 加藤 司 |
| 人びとの営みの中にこそ潜む政策的インプリケーション | 佐藤彰彦 |
| 東日本大震災における岩手県・消費者信用生協の取り組み──釜石相談センター訪問レポート── | 松本 進 |
| 東日本大震災以後の被災地での雇用をめぐる状況について──岩手県ならびに釜石周辺を中心に── | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年4月号「震災1年―くらしとまちの再建へ」 | 井上 清美 |
| 2012年4月号「震災1年―くらしとまちの再建へ」 | 西村 一郎 |
| ■シリーズ・現代社会と生協──国際協同組合年に向けて(9) | |
| 地域社会づくりと生協 | 金子隆之 |
| ■日本生協の国際協力の歩みVol.2 | |
| 共済生協の国際協力──全労済のケース── | 高野 智 |
| ■残しておきたい協同のことば 第15回 | |
| エミー・フロイントリッヒ | 鈴木 岳 |
| ■研究所日誌 | |
2012年5月号(Vol.436)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 再び,東日本大震災に寄せて | 大石芳裕 |
| ■特集 東日本大震災と生協の共済 | |
| 東日本大震災と生協共済のビジネスモデル | 岡田 太 |
| 巨大災害時における協同組合・共済の役割 | 宮地朋果 |
| 東日本大震災における保険と共済の取り組み | 江澤雅彦 |
| 公開研究会を終えて──残された検討課題── | 甘利公人 |
| 東日本大震災における全労済の取り組みと今後の課題 | 高野 智 |
| 東日本大震災におけるCO・OP共済の取り組み | 小塚和行 |
| 「東日本大震災」への大学生協および大学生協共済連の取り組みについて | 鈴木洋介 |
| ■日本生協の国際協力の歩みVol.1 | |
| 日本生協の国際協力の歩み──序論── | 栗本 昭 |
| ■残しておきたい協同のことば 第14回 | |
| ジョゼフ・ルメール | 鈴木 岳 |
| ■私の愛蔵書 | |
| E.F.シューマッハー著 『スモールイズビューティフル』 | 林 薫平 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年3月号特集「多重債務相談・貸付事業研究会を終えて」 | 河原 洋之 |
| ■研究所日誌 | |
2012年4月号(Vol.435)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 建設業の新展開で老若男女の雇用機会を | 大沢 真理 |
| ■特集 震災1年──くらしとまちの再建へ | |
| 東北住宅復興の論点 | 平山 洋介 |
| 現場からの復興イニシアチブ──石巻中心街での経験から考える── | 真野 洋介 |
| 東日本大震災被災地におけるフードデザート問題 | 佐々木 緑 |
| 大船渡への支援行動で被災地の生活課題,健康問題を考える | 金丸 正樹 |
| 東日本大震災における子ども支援 ──東日本大震災子ども支援ネットワークと山田町ゾンタハウスでの取り組みを手掛かりにして── |
森田 明美 |
| 被災地域の子育て支援を再構築する動き──甚大な津波被害をうけた宮城県石巻市を事例に── | 近本 聡子 |
| ■シリーズ・現代社会と生協──国際協同組合年に向けて(8) | |
| 地域福祉・高齢者福祉と生協の役割 | 山際 淳 |
| ■海外のくらしと協同No.33(最終回) | |
| タイ国の社会保障制度の概要 | 佐藤 史子 |
| ■残しておきたい協同のことば 第13回 | |
| アルビン・ヨハンソン | 鈴木 岳 |
| ■本誌特集を読んで | |
| 2012年2月号「福島原発事故以後のエネルギー問題を考える」 | 當具 伸一 |
| 2012年2月号「福島原発事故以後のエネルギー問題を考える」 | 林 薫平 |
| ■研究所日誌 | |