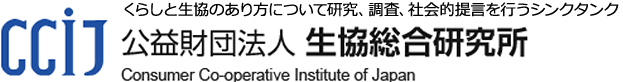刊行物
【新刊のご案内】『地域学習支援論―学び合える社会関係のデザイン』
荻野亮吾、近藤牧子、丹間康仁 編著

「人生100年時代」といわれる今日、高齢期の生き方や働き方を考えることは、私たちに無縁なことではなくなりました。特に近年、社会人の学び直しの重要性が指摘され、リスキリングやリカレント教育といった概念に注目が集まるなど、若年期にとどまらず中年・高齢期も含めた長いタイムスパンで、教育や学習を捉える必要が生じています。このような背景をうけて、本書は、そもそも社会人の学び直しとは何か、学校外の場(地域、職場、オンラインなど)での学びをどう捉えるのかといった点についてまとめています。
本書は、大学での教員養成課程や社会教育主事養成課程、教職大学院の演習、さらには現職教員や教育委員会等での活用を想定した入門・基礎レベルのテキストとして作成されていますが、どのような読者にも読みやすい内容になっています。また、別冊電子版のワークシートが付属しており、印刷して授業やワークショップなどで利用できるようになっており、非常に実用性が高くなっています。
高齢化が進み、生活様式も多様化する中で、今日の社会において、誰しもが自身の将来の生き方や働き方を考える必要に迫られています。本書はそれらを考える際の参考となると考えます。是非、多くの方に手にとっていただければ幸いです。
※第Ⅳ部第6講「子育て支援を通じて地域のつながりをどう育むか?」を弊研究所研究員の中村由香が執筆しています。 |
2025年3月21日発行 A5判・252ページ
定価(本体2,300円 + 税)
ISBN:978-4-86692-344-4
発行:大学教育出版
主な目次
- 第Ⅰ部 生涯にわたる学びをどう理解するか?
- 第1講 すべての人の生涯にわたる教育とは?
第2講 学びを生み出す仕組みとは?
第3講 大人はどう発達するか?
第4講 働く世代はどう学ぶか?
第5講 市民としての成長には何が求められるか?
第6講 大人の「学びなおし」をどう支えるか? - 第Ⅱ部 学び合いをどうつくるか?
- 第1講 対話に基づいた学びをどうつくりあげるか?
第2講 学びに向けてどう学習者に問いかけるか?
第3講 学び合うワークショップをどう組み立てるか?
第4講 対話と学びの「環境づくり」をどう進めるか?
第5講 オンラインでの学び合いの「環境づくり」をどう進めるか?
第6講 ふりかえりはなぜ大切なのか?
第7講 学習の評価をどう行うか? - 第Ⅲ部 地域と学校で子ども・若者をどう育てるか?
- 第1講 小・中学生の「ふるさと教育」をどう進めるか?
第2講 高校生のプロジェクト型学習の支援をどう進めるか?
第3講 大学と地域での学びをどう進めるか?
第4講 子どもの放課後の学びをどう支えるか?
第5講 多様なバックグラウンドをもつ子どもたちの学びと生活をどう支援するか?
第6講 外国ルーツの子ども・若者たちの明るい将来ビジョンをどう育むか?
第7講 地域と学校の「協働」をどう深めるか? - 第Ⅳ部 地域に持続可能な実践をどうつくりだすか?
- 第1講 学びを止めないためにどんな支援が大切か?
第2講 当事者の経験をどう言語化するか?
第3講 被災地における支援をどう継続するか?
第4講 障害者の学習を地域でどう支え続けるか?
第5講 高齢者を中心とした地域活動をどう継続するか?
第6講 子育て支援を通じて地域のつながりをどう育むか?
第7講 ユースワーカーの省察をどう支援するか?
第8講 地域の変革に向けた学習の循環や継続をどう生み出すか?)
執筆者
荻野 亮吾 (日本女子大学)〔編者〕
近藤 牧子(認定NPO法人開発教育協会)〔編者〕
丹間 康仁 (筑波大学)〔編者〕
森 玲奈 (帝京大学)
中村 絵乃 (認定NPO法人開発教育協会)
上條 直美(フェリス女学院大学)
古田 雄一(筑波大学)
斉藤 雅洋(高知大学)
鈴木 瞬(金沢大学)
池田 春奈(NPO法人ダイバーシティ工房)
大森 容子(公益財団法人滋賀県国際協会)
林 美帆(岡山理科大学)
似内 遼一(東京大学)
正木 遥香(流通経済大学)
菅原 育子(武蔵野大学)
中村 由香(公益財団法人生協総合研究所)
佐渡 加奈子 (認定NPO法人カタリバ)
南 信乃介(那覇市繁多川公民館)
(所属は2024年10月現在)
本書のご注文について
お近くの書店でご注文ください。大学教育出版ホームページからもご購入いただけます。