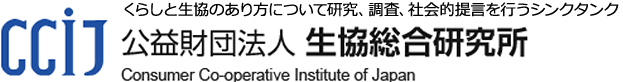- ホーム
- 刊行物情報
- 生活協同組合研究バックナンバー一覧
- 1994年度
生活協同組合研究バックナンバー一覧
1994年度
1995年3月号(Vol.230)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 基本に戻ることの大切さ | 野村 秀和 |
| シリーズ転換期の生協とマネジメント(第3回) | |
| 新しい社会運動としての組合員活動と職員組織-ライフスタイルの創造とジェンダーの視点 | 佐藤 慶幸 |
| 生協運動と地域形成の課題 | 矢澤 修次朗 |
| ■インタビュー(第42回) | |
| 国連社会開発サミットの課題と日本の社会的部門 | 西川 潤 |
| ■特集 新しい時代の仕事のあり方と職員問題 | |
| 労働概念の変換を考える | 大内 力 |
| 生協労働と職員問題研究会を終えて-今後の課題- | 兵藤 釗 |
| 職員問題とトップマネジメント | 山下 俊史 |
| 人事制度と労働組合 | 大西 憲慈 |
| 「パネルデイスカッション」生協経営における職員問題 | |
| 民主的経営と職員の役割発揮 | 角瀬 保雄 |
| 生協労働を考える | 三好 正巳 |
| ■海外協同組合事情 | |
| 東ヨーロッパ協同組合運動の構造変化 | タデウス・コアラク 抄訳;石塚 秀雄 |
| ■文献紹介 | |
| 『家族の変化と生活経済』 | 近本 聡子 |
| 「1994年度総目次」 | |
| ■研究所日誌 | |
1995年2月号(Vol.229)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 協同組合の国際的連帯と研究の強化を思う | 野原 敏雄 |
| シリーズ転換期の生協とマネジメント(第2回) | |
| トップマネジメントとガバナンス-経営学における最近のトップマネジメント論の焦点- | 加護野 忠男 |
| 参加型市場経済と生協の役割 | 飯尾 要 |
| 家族はどう変化しているか | 岡崎 敬子 |
| ■インタビュー(第41回) | |
| 主人公としての消費者~消費者教育の展望と課題 | 植苗 竹司 |
| ■研究会報告 | |
| 規制緩和をめぐる視点 | 正田 彬 |
| ■海外協同組合事情 | |
| ホレイス・プランケットとプランケット協同組合研究財団創立75周年をめぐって | 今井 義夫 |
| 生協の社会的貢献と寄付講座 | 白井 厚 |
| 最近の食料・農業事情 | 大嶋 茂男 |
| ■文献紹介 | |
| 河田禎之 著『物語 城西消費組合』 | 西村 一郎 |
| ■研究所日誌 | |
1995年1月号(Vol.228)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「仕事」と「稼ぎ」 | 大内 力 |
| 日本の生協の現状と課題 | 野村 秀和 |
| 共同組合経営の現段階と経営者問題 | 岡本 好廣 |
| 論評 規制緩和と生協の流通政策 | 岩下 弘 |
| ■インタビュー(第40回) | |
| カイロ会議から北京女性会議へ ~NGOの活躍~ | 樋口 恵子 |
| ■海外共同組合事情 | |
| 台湾の生協の現状と新しい運動の動向 | 丸山 秀樹 |
| アメリカ 「1995年農業法」の焦点 | 持続可能な農業の全国調整委員会 翻訳;福重 直子,横川 洋 |
| 環境を守る合意形成の方式 -カナダの事例- | カナダ環境省・「環境と経済の円卓会議」 翻訳;石塚 秀雄 |
| インフォメーション 中国市場学界の紹介 | 保田 芳昭 |
| ■文献紹介 | |
| 河野 直践著『協同組合の時代-近未来の選択』 | 大木 茂 |
1994年12月号(Vol.227)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| コメの生産と消費を考える -創立5周年記念シンポジウムから- | 伊東 勇夫 |
| いわて生協の取り組みとシリーズの感想 | 杉村 洋一 |
| 学んだことと実践課題 | 針川 佐久眞 |
| 青年の立場からみた生協運動 | 盛本 達也 |
| 賃金労働者という本質と生協職員としての特質について | 長崎 清一 |
| 組織合同における職員処遇上の政策 | 北島 高茂 |
| “ぶつかりあい”から生まれるもの | 宮崎 省三 |
| 大学生協の職員政策の現状と課題 | 小塚 和行 |
| シリーズを読んで | 平田 昌三 |
1994年11月号(Vol.226)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 「第3の道」と協同組合 | 野尻 武敏 |
| 職員問題アンケートを実地して | 柳沢 敏勝 |
| 「生協労働と職員問題」の一考察 | 西村 一郎 |
| 米と農業のアンケートから -コープさっぽろの主張- | 高橋 勝巳 |
| 米の年間利用登録制度についての報告 -みやぎ生協- | 伊藤 勝巳 |
| 特別栽培米の取組みから -市民生協にいがた- | 小川 洋三 |
| 佐賀における環境の保全と産直米2倍への取り組み -コープさが- | 松本 司 |
| 論評 生協と政治に関する見解 | 重原 祐治 |
| 論評 宮崎県民生協の提起するもの -これからの生協のあり方を問う- | 高橋 晴雄 |
| ■インタビュー(第38回) | |
| 協同組合研究の国際的な発展を | イアン・マクファーソン |
| ■研究会報告 | |
| 首都圏コープ産直の現状と問題点 | 岡田 哲郎 |
| ■文献紹介 | |
| E.U.フォン・ワイツゼッカー著『地球環境政策』 | 大嶋 茂男 |
1994年10月号(Vol.225)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 野生生物保護をめぐる動向 | 本谷 薫 |
| 新人事制度を考える背景 | 増田 大成 |
| コープこうべにおける新人事制度 | 杉尾 哲男 |
| 聴くことでどんな変化が-生活と労働の場で- | 高橋 晴雄 |
| 環境保全と調和する持続可能な農業をめざして | 嘉田 良平 |
| ウルグアイ・ラウンド交渉を通して知った環境・消費者・生産者のネットワークの広がり | 伊庭 みか子 |
| 対談 ガット以降の世界の食料・農業 | 嘉田 良平,伊庭 みか子 |
| 瀬戸際の食管制度 ~「改廃」をめぐる諸『提言』について~ | 笹野 武則 |
| 論評 ドイツ協同組合の監査制度 | 小楠 湊 |
| ■インタビュー(第37回) | |
| 躍動感にあふれる生協を | 日和佐 信子 |
| ■研究会報告 | |
| みやぎ生協の基本商品政策(農産) | 太田 徹夫 |
| インフォメーション 全労済組合員の暮らしと意識に関する調査 | 近本 聡子 |
| ■文献紹介 | |
| 一番ヶ瀬康子著『生涯福祉・ノーマライゼーション』 | 西村 一郎 |
| 『シーフードの新時代』 『EC食品産業の野望』 | 大木 茂 |
1994年9月号(Vol.224)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 生き方を支える生協へ | 暉崚 淑子 |
| 生き生きと働ける生協職場を求めて -労働組合から見る「生協職員論」- | 鈴木 彰 |
| 労働者組合の現状と課題 -「労働と企業の未来」を中心に- | 菅野 正純 |
| ガット締結後の日本農政の方向 | 児玉 一彌 |
| 米を考える-米卸としての立場から- | 釜谷 弘 |
| 食管制度-この1年で方向付け迫られる- | 荒田 盈一 |
| 米の消費・生産の基本構造と米政策 | 茅野 甚治郎 |
| 論評 協同組合原則の「改正案」論考 | 伊東 勇夫 |
| ■インタビュー(第36回) | |
| 持続可能な農業への道を拒むガット合意 | リンダ・エルスウィック |
| ■文献紹介 | |
| 最近の生活協同組合関連主要文献 | 石塚 秀雄 |
1994年8月号(Vol.223)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 家庭内分業の克服を願う | 塩田 長英 |
| シリーズ「生協労働を考える」(第8回)宮崎県民生協の実践から何を学ぶか | 兼子 厚之 |
| 地域生協における職員問題を考える | 佐藤 信・大高 研道 |
| みやぎ生協における職員問題 | 芳賀 唯史 |
| 連載米問題の研究(第6回)農協の農政運動の「挫折」と再生の方向い | 佐伯 尚美 |
| 制度改革の課題といくつかの論点 | 吉田 俊幸 |
| 論評流通業の地殻変動と生協経営 | 岡本 好廣 |
| 激動する流通構造ー卸売市場制度の変容過程と再編方向ー | 細川 充史 |
| ■インタビュー(第35回) | |
| 日本の食糧基地としての北海道農業 | 藤野 貞雄 |
| 研究資料アジアにおける稲作経済の発展 | マハバブ・ホセイン |
| ■文献紹介 | |
| 『生協産直とグリーンライフ』日本生協連企画編集 | 大木 茂 |
1994年7月号(Vol.222)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 平成不況の性格 | 花原 二郎 |
| シリーズ生協労働を考える(第7回)知識創造の経営 | 野中 郁次郎 |
| コープさっぽろにおける職員問題 | 河村 征治 |
| 連載米問題の研究(第5回)平成コメ騒動の教訓と食糧管理制度の立て直し策 | 渡辺 信夫 |
| 契約栽培米の新しい試み | 吉田 義男 |
| 参加型民主主義の確信を目指して | 山岸 正幸 |
| 協同組合による農水産物輸入についてー日・タイ農協間貿易からの教訓ー | 山本 博史 |
| ■インタビュー(第34回) | |
| カーソンの思想を語りつぐ | ダイアナ・ポスト |
| 研究資料お正月の意識と食品購入 | 近本 聡子 |
| ■文献紹介 | |
| 秋川実著『農薬に挑む』 | 渋谷 長生 |
1994年6月号(Vol.221)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 飽食の裏側 | 安井 勉 |
| シリーズ「生協労働を考える」(第6回)生協における「生産力」と労働条件 | 大西 広 |
| コープとうきょうにおける職員問題 | 山下 俊史 |
| オウエン研究と協同組合 | 都築 忠七 |
| ロバート・オウエンの人間論と教育 | 土方 直使 |
| G.J.ホリヨークにおける経済・宗教・教育 | 杉本 貴志 |
| ロッチデール公正先駆者組合と教育 | 中川 雄一郎 |
| 連載:米問題の研究(第4回)生協のコメ問題シンポジウムが語りかけるもの | 編集部(大木) |
| 論評社会的経済と協同組合の役割 | 富沢 賢二 |
| ■インタビュー(第33回) | |
| イギリス女性運動史」と私 | 今井 けい |
| ■研究会報告 | |
| ヨーロッパの協同組合経営に関わる諸問題 | 角瀬 保雄 |
| インフォメーション持続可能な社会を作る道すじ | 大嶋 茂男 |
| ■文献紹介 | |
| G.フオーケ著「協同組合セクター論 | 大谷 正夫 |
| G.ホリヨーク著「ロッチデールの先駆者たち」 | 中西 啓之 |
| 大嶋・村田著「消費者運動のめざす食と農 | 伊東 勇夫 |
1994年5月号(Vol.220)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 生協福祉活動の「基本的価値」 | 一番ケ瀬 康子 |
| 欧米の商業労働者ーアメリカ・モデルとヨーローッパモデルー | 三富 紀敬 |
| フランスの労働者協同組合における労働者のイニシアチブ | 石塚 秀雄 |
| 連載米問題の研究(3)米問題の終点をどう考えるか | 速水 佑次郎 |
| 連載米問題の研究(3)米問題素朴な疑問 | 藤澤 光治 |
| コメの市場開放と今後のコメ政策 | 森島 賢 |
| ■インタビュー(第32回) | |
| 価値観をもつから未来がある | 嶋田 啓一郎 |
| 論評製造物責任法ーEC指令の特徴と残された課題 | 新田 俊三 |
| 社会的ヨーロッパの建設と「社会的経済」理論 | 西川 潤 |
| 海外情報スウエーデンにおける生協小売流通の現状と改革の進展 | 雲栄 道夫 |
| 二重目的のアドバイザー機関 | オーヴエ・ヨーブリング |
| 協同組合開発活動のいくつかの経験 | エヴァ・テルネグレン |
| ■文献紹介 | |
| 細川充史著「変貌する青果物卸売市場」 | 大木 茂 |
1994年4月号(Vol.219)
| ■巻頭言 | |
|---|---|
| 生協職員経営参加 | 外尾 健一 |
| 生協労働の今日的課題 | 永山 利和 |
| 現代の雇用状勢と協同組合 | 編集部(大島茂男) |
| ■特集 | |
| 消費者の権利消費者の権利とはー現代日本の法秩序における位置づけー | 宮坂 富之助 |
| 消費者の権利ー国際非較、PL法、消費者の被害救済を中心に | 清水 誠 |
| 消費者の権利をまもる行政制度 | 鈴木 深雪 |
| 日本における消費者の権利と裁判 | 宮本 康昭 |
| 日本における消費者の権利の歴史現状課題 | 正田 |
| 連載米問題の研究(第2回)生活協同組合と農業食糧問題ーコメ輸入自由化問題を中心に | 田代 洋一 |
| 人づくりと協同のネットワーク | 佐藤 一子 |
| 西ヨーロッパ協同組合運動の構造的変化と協同組合法制の重要性 | ハンス・H・ミュンクナー |