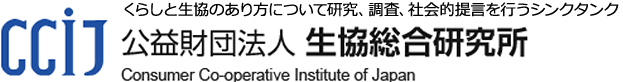- ホーム
- 刊行物
- 生協総研レポートバックナンバー一覧
- 生協総研レポート No.51~60
刊行物
生協総研レポートバックナンバー一覧
生協総研レポート No.51~60
(各論考のタイトルをクリックするとJ-STAGEに公開されている当該論考のPDFをご覧になれます)
生協総研レポート No.60(2009年3月刊行)
| 生協の社会的役割を問う―2008年度現代生協論コロキアムの成果― | |
|---|---|
| はじめに | 石川 廣 |
| 第1部 第5回現代生協論コロキアム「市民社会における生協の役割」 | |
| 開催概要・参加者名簿 | |
| 開会挨拶:生協学のめざすもの | 蓮見 音彦 |
| 問題提起I 希望の構想とソーシャル・ガバナンス:市民全体の社会経済システムの形成に向けて |
神野 直彦 |
| 問題提起II 「21世紀型消費者政策」の展開と「消費者力」への期待 |
田口 義明 |
| 報告に対するコメント | 大沢 真理 |
| 報告に対するコメント | 宮本 太郎 |
| 報告に対するコメント | 宮坂富之助 |
| コメントに対する回答 | 神野 直彦 |
| コメントに対する回答 | 田口 義明 |
| 討論 | |
| 第2部 第6回現代生協論コロキアム「生協商品におけるクライシス対応と組織・連帯構造」 | |
| 開催概要・参加者名簿 | |
| 開会挨拶:第6回コロキアムへの期待 | 神野 直彦 |
| 問題提起I 日本の生協のクライシス対応と組織・連帯構造 |
若林 靖永 |
| 問題提起II ギョーザ事件の現地から生協のクライシス対応と組織・連帯構造を考える |
田井修司 |
| 報告に対するコメント | 島岡勤 |
| 討論 | |
生協総研レポート No.59(2009年1月刊行)
| 「子育てひろば」の効果測定 全国5都県利用者調査報告書 | |
|---|---|
| はじめに | 石川 廣 |
| 第一部 調査からみえること | |
| 子育てひろばの効果に関する調査研究の試み | 福川 須美 |
| 調査概要と回答者のプロフィール | 近本聡子 |
| 子育てひろば(サロン)の効果測定 「ひろば効果尺度」の開発 |
斎藤 進 |
| 「常設型ひろば」と「月数回ひろば」 タイプ別にみたひろばについての考察 |
渡辺 寧・加藤 雅代・関 一子 |
| 生協の子育てひろばの状況と効果・課題や可能性 | 渡部 典子 |
| 第二部 データ詳細分析から | |
| ひろばからどこへ向かうのか:仕事志向と子育てサークル・活動志向のはさまで | 相馬 直子 |
| ひろばがもたらす効果の特性についての考察 | 赤井美智子 |
| 「初めて子育て」を支える子育てひろば | 近本 聡子 |
| 自由記述からみる「ひろば」のあり方の検討 | 永田 陽子 |
| 子育て支援施策におけるひろば型支援の拡大と課題 | 福川 須美 |
| 巻末データ | |
| 調査票 | |
生協総研レポート No.58(2008年9月刊行)
| 「生協における働き方研究会」報告書 | |
|---|---|
| 「生協における仕事のあり方研究会」の報告にあたって | 石川 廣 |
| 生協における仕事のあり方を考える | 麻生 幸 |
| 「生協における働き方調査」の分析 | 西村 一郎 |
| 一般企業と比較した生協の職場と仕事 | 高田 一夫 |
| ジェンダーからみた生協の職場と仕事 | 禿 あや美 |
| 生協における職員の仕事満足に関する多変量解析 ――正規職員,パート職員,及び委託職員の各雇用形態における要因の相違に注目して―― |
山縣 宏寿 |
| 職員・労働組合の立場から | 桑田 富夫 |
| 「生協における働き方調査」の調査結果を現場はどう見たか | 占部 修吾 |
| パートにとって働きやすい職場とは?――職場の現状と労組の取り組みから―― | 上田 秋江 |
| 生協における働き方をめぐって | 當具 伸一 |
| 今日の生協の職場と仕事の関係について | 大山 克己 |
| 委託会社社員を対象にした「生協における働き方調査」の分析と課題 | 吉村 邦雄 |
| 生協職員の働きがい阻害要因とその改善策 ―Great Place to Work Institute「働きがいのある会社モデル」の枠組みを基に― |
小野 好秀 |
| *資料 (1)調査表(男女別の回答) (2)研究会の概要 |
|
生協総研レポート No.57(2008年3月刊行)
| 事業と法制度の変化と生協学 ――2007年度現代生協論コロキアムの成果―― |
|
|---|---|
| はじめに | 藤岡 武義 |
| 第1部 第3回現代生協論コロキアム(5/12) | |
| 開会挨拶:第3回コロキアムの開始にあたって | 蓮見 音彦 |
| 問題提起 I フードシステム論からみた生協 | 生源寺 眞一 |
| 問題提起 II 現代の生協事業の特性を再検討する | 若林 靖永 |
| 報告に対するコメント | 斎藤 修 |
| 報告に対するコメント | 新津 重幸 |
| 報告に対するコメント | 木立 真直 |
| 報告に対するコメント | 吉野 源太郎 |
| 報告に対するコメント | 浜中 淳 |
| 報告に対するコメント | 矢野 和博 |
| 討論:生協事業の現代的展開 | |
| 第2部 第4回現代生協論コロキアム(11/17) | |
| 開会挨拶:第4回コロキアムの開始にあたって | |
| 問題提起 I 生協法改正の意義を考える | 宮坂 富之助 |
| 問題提起 II 生協法改正と機関構成 | 関 英昭 |
| 問題提起 III 生協法改正の背景と意義 | 栗本 昭 |
| 報告に対するコメント | 麻生 幸 |
| 報告に対するコメント | 若林 靖永 |
| 報告に対するコメント | 品川 尚志 |
| 討論:生協法改正の意義と課題 | |
生協総研レポート No.56(2008年3月刊行)
| 生協の子育て支援事例報告集 | |
|---|---|
| はじめに | |
| イントロダクション | |
| 第一部 子育て支援で地域でのネットワークを広げる | |
| ポラン農業小学校のとりくみ | 吉田 敏恵 |
| 東京マイコープの保育 | 鈴江 茂敏 |
| こども110番のとりくみ | 塩道 琢也 |
| トライやる・ウィークでの地域との協働 | 鈴木 洋子 |
| 第二部 地域に根ざした子育て支援事業・活動の展開 | |
| みやぎ生協の子育て支援 「子育てふれんず」を中心に | 佐藤 妙子 |
| ちばコープの子育て支援 リラックス館を中心に | 加藤雅代・渡辺 寧 |
| 第三部 既存事業による子育て層へのアプローチ強化 | |
| パルシステムの3媒体:なぜ3媒体か? | 金田 邦夫 |
生協総研レポート No.55(2008年2月刊行)
| 生協産直を支える生産者の取り組み 第7回全国生協産直調査における事例調査から | |
|---|---|
| 発刊に当たって | 藤岡 武義 |
| 少量多品目型産消近接産直の到達点――みやぎ生協とJAみやぎ仙南の産直活動 | 中嶋康博 |
| 生協事業連合進展下における産直産地のマーケティング対応と今後の課題――多古町旬の味産直センターの事例 | 木立真直 |
| 紀ノ川農協の展開にみる生協の提携課題 | 大木茂 |
| 生協産直の変化とトップランナーの戦略――ながさき南部生産組合の事例 | 佐藤和憲 |
| 後発の大規模産直産地の出現とその意味――JA八女の事例 | 森江昌史 |
生協総研レポート No.54(2007年3月刊行)
| 生協学の確立へ向けて―2006年度現代生協論コロキアムの成果 ― | |
|---|---|
| はじめに | 藤岡 武義 |
| 第1部 第1回現代生協論コロキアム(5/17) | |
| イントロダクション:生協学のめざすもの | 蓮見 音彦 |
| 報告1:組合員のくらしの変化と組合員活動 | 二村 睦子 |
| 報告2:生協事業は組合員の変化に応えているか | 田井 修司 |
| 報告に対するコメント | 矢野 和博 |
| 討論 | |
| 第2部 第2回現代生協論コロキアム(11/11) | |
| 開会挨拶:第2回コロキアムの開始にあたって | |
| 解題:生協学へのアプローチ | 宮坂 富之助 |
| 問題提起1:生協学の研究姿勢 | 生源寺 眞一 |
| 問題提起2:現代生協論をめぐって:生活保障システムという枠組み | 大沢 真理 |
| 問題提起3:生協とは何だろう:『消費者の協同組合』の原理的検討 | 川口 清史 |
| 報告に対するコメント | 小栗 崇資 |
| 報告に対するコメント | 藤井 敦史 |
| 報告に対するコメント | 今野 聰 |
| 報告に対するコメント | 若森 資朗 |
| 報告に対するコメント | 嶋田 裕之 |
| 討論:生協学をどう確立するか | |
生協総研レポート No.53(2007年3月刊行)
| 市民生協の創設と発展:元リーダーに聞く第2集 | |
|---|---|
| はじめに 「市民生協の創設と発展:元リーダーに聞く」について | 藤岡 武義 |
| 千葉県での市民生協の新設と再生 | 高橋 晴雄, 清水 旻 |
| 静岡での市民生協づくりと県内の大同団結 | 上田 克巳, 加藤 恒一 |
| 大学生協からグリーンコープ生協グループの形成へ: 福岡と九州での協同連帯の推進役として |
魚屋 忠久 |
| 群馬県の市民生協の発展:経営の健全化と連帯の促進 | 木原 勇司, 峰岸 通 |
| 「ロマンとそろばん」を胸に,「協同組合のあるまちづくり」に挑戦 | 山中 洋 |
| 生活クラブ生協の歴史と理念:自発性の高い協同組織を目指して | 折戸 進彦 |
| 生活者としての生協運動と男女共同参画の意味 | 立川 百恵 |
| 県連主導の市民生協づくり | 冨田 巖 |
| 「多様性の共存」を理念に: 連帯と個配で発展してきたパルシステム・グループ |
下山 保 |
| 「有言実行」をモットーに生協再建と民主的運営の追求 | 後藤 四六 |
| 『市民生協の創設と発展』を振り返って | 川口 清史, 藤岡 武義 |
生協総研レポート No.52(2006年11月刊行)
| 変化する青果の流通構造 | |
|---|---|
| 青果物の流通の変化と戦略的な課題:フードシステムの視点から | 斎藤修 |
| 生協事業の特徴と課題:コープネットとパルシステムにおける青果物・米事業比較 | 大木 茂 |
| パルシステムの農産事業と産消提携事業 | 高橋宏通 |
| コープネット事業連合の農産事業 | 深澤米男 |
| 変化する青果物流通における市場の役割 | 本岡俊郎 |
| 輸入青果物と国内流通 | 西影昌純 |
| カゴメの生鮮トマト事業 | 尾崎泰弘 |
| 生協の青果売場:ヨークベニマルとの比較を中心に | 折戸 功 |
| 野菜に関するインターネット調査 | |
| 青果の流通構造研究会の概要 | |
生協総研レポート No.51(2006年1月刊行)
| 高齢者の食と健康の状態と生協の課題:高齢者の食と健康研究会報告書 | |
|---|---|
| 発刊にあたって | 高齢者の食と健康研究会 |
| 第一部 調査について | |
| 1.調査結果について | 西村 一郎 |
| 2.食行動と健康 | 須田 木綿子 |
| 第二部 調査から明らかになったことやアドバイス | |
| 1.高齢者の食の大切さ | 八倉巻 和子 |
| 2.高齢者の食事 | 町野 美和 |
| 3.高齢者の料理教室を支援して | 清水 紀子 |
| 4.調査から明らかになったことと医療生協の課題 | 安岡 淳一 |
| 5.「高齢者の食と健康アンケート」結果から高齢協として何をするか | 片山 信一 |
| 6.10年後20年後の高齢者も含めて、地域生協の活きる意味 | 平田 壽子 |
| 第三部 資料 | |
| 1.データ(性別年齢別)、クロス集計 | |
| 2.自由記入 | |
| 3.アンケート用紙 | |
| 4.研究会について | |
出典:生協総研レポート 出版:生協総合研究所